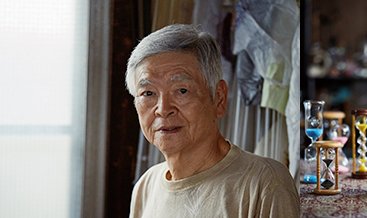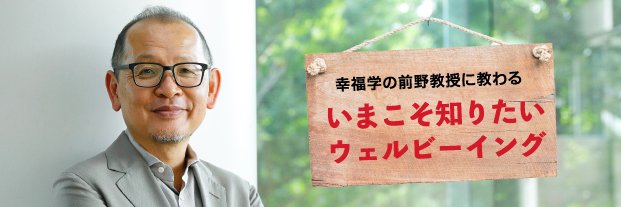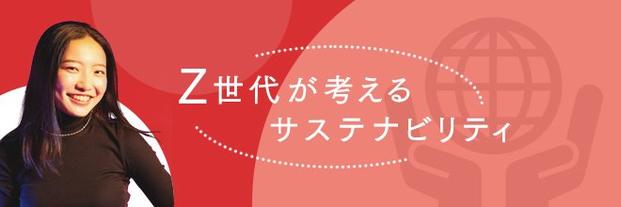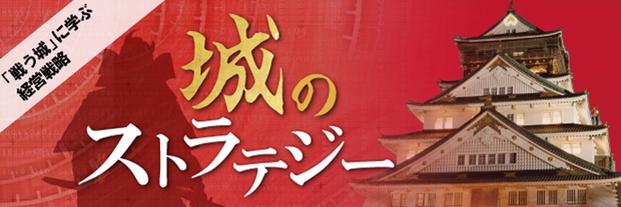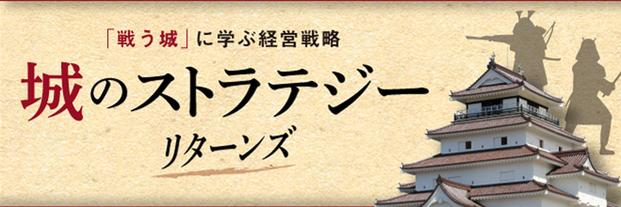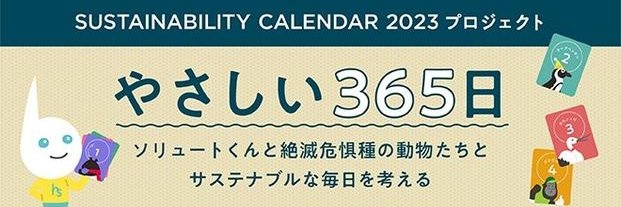※本記事は2019年7月に掲載されたものです
「何をやるか」よりも「何をやらないか」が重要
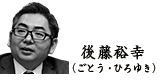 1978年熊本県生まれ。中央大学法学部政治学科在籍時に起業し、28歳でグローバルトラストネットワークス(GTN)を設立。外国人向けの賃貸住宅保証ビジネスからスタートし、生活サポート、賃貸仲介、携帯電話、人材紹介、クレジットカードなど、日本に住む外国人をサポートする各種事業を展開している。 |
──外国人向けの保証ビジネスを始めたきっかけをお聞かせください。
以前私が経営していた会社の社員は、私以外ほとんど外国人でした。彼らと一緒に飲みに行くと「保証人がいなくて部屋が借りられない」と皆、口をそろえて言うんです。それなら私が保証人になろうと立ち上げたのがGTNです。主な顧客は不動産管理会社で、外国人と入居契約をする際に連絡をいただき、審査をして問題がなければ保証人を引き受けます。
──リスクはないのでしょうか。
当社のスタンスは「親代理業」です。保証人は一般的には親に頼むものですよね。しかし、外国人の場合は本国に親がいるので頼むことができません。そこで、私たちが本国の親と直接連絡を取って、連携が可能と判断した場合のみ保証人になります。
──なるほど。本当の親との連携のもとでの「親代わり」だからリスクは非常に少ないわけですね。保証事業以外のビジネスも手がけているのですか。

世界各国の国旗があしらわれたカップ。こんなところにもGTNの多様性が表れている
|
基幹事業は他に3つあります。まず、保証ビジネスから発展した不動産賃貸仲介業。次に、外国人向けの通信事業。代理店ではなく自ら通信事業者(MVNO)になるという事業モデルです。そして3つ目が、外国人の働き手を企業に紹介する人材ビジネスです。他に、最近では外国人向けのクレジットカード事業も始めました。
──日本に来る外国人は、GTNに相談すれば基本的な生活がすべて整うということですね。前例のないビジネスである分、苦労も多かったのではないですか。
2006年の創業時には毎日飛び込み営業をしていましたが、全く相手にされませんでしたね。外国人は生活トラブルが多いとか、物件価値が下がるとか、ここでは言えないようなもっと差別的なことを言う人もいました。最初の3カ月での契約は1件だけ。売り上げは4万5000円でした。
しかし創業から12年半ほどたって、今では私たちのビジネスは広く認知されるようになっています。取引のある不動産会社はおよそ1万店で、これまでの保証契約件数は12万件に達しています。大学との連携も進んでいて、現在63校と提携しています。
──ニッチと言っていいビジネスだと思いますが、成功の要因は何だったのでしょうか。
「何をやるか」よりも「何をやらないか」を明確にしたことだと思います。保証ビジネスを始めた頃、「どうして日本人の保証はしないんだ?」とよく聞かれました。しかし対象を日本人まで広げていたら、GTNのビジネスはかなりぼんやりしたものになっていたと思います。外国人だけを対象にする。日本人は対象にしない。それにこだわったからこそ、エッジが立って、目立つことができたわけです。これまでの何度かの起業経験で学んだことは、ビジネスはオンリーワンをめざすべきだということです。オンリーワンということは、競合がいないということですから、おのずとナンバーワンになれるのです。

壁紙や調度品に工夫が凝らされているGTNのオフィス。「明るく、楽しく働いてほしい」という後藤氏のメッセージが込められている。壁紙の「510」という数字は「ゴトウ」を意味するとか
|
外国人がいなければ日本の経済は成り立たない
──創業以来、日本の外国人を取り巻く状況はどう変わりましたか。
まず、数が違います。中長期在留者数は231万人を超えました(2018年6月時点)。外国人が特に多い東京23区では、新成人のほぼ8人に1人が外国人になっています。新宿区の新成人の4割超、同じく豊島区の新成人も約4割が外国人です。
外国人自体も1年間で十数万人増えています。10年前は居酒屋などで外国人が働いている姿を目にすることはほとんどありませんでしたが、今はコンビニでも普通に働いています。社会の中に外国人がいる風景がごく当たり前のものになっているわけです。
こうなると、当然日本人のメンタリティーも変わります。日本人の多くが、隣人や同僚として外国人を受け入れるようになってきていると思います。
 |
──2018年には出入国管理法が変わり、日本は事実上の移民社会に向けて舵を切りました。この動きをどう見ていますか。
基本的にはポジティブに受け止めています。単身者の上限5年の滞在が許される「特定技能1号」という資格では、14業種での労働が認められることになりました。まずは「外食」「宿泊」「介護」の3業種での技能試験が実施されますが、その結果、何が起こるか。まず、工場や事業所のバックヤードではなく、接客の現場で多くの人が外国人を日々目にするようになります。これによって、ますます外国人はごく普通の住民として認知されるようになるでしょう。
また、介護現場で外国人が働くことの影響も大きいと思います。高齢者が日常的に外国人と接するようになり、体を洗ってもらったり、おむつを替えてもらったりする。そういう経験をすることで、これまで外国人に偏見を持ちがちだった高齢者の意識も大きく変わっていくはずです。
──今後、日本の人口が減っていくことを考えれば、外国人に働いてもらうことは必然といえそうですね。
その通りです。日本の人口は2050年に約9700万人まで減ると予想されています。減少数は平均すると毎年100万人。政令指定都市が年に1つ消滅するのと同じです。
一方、世界の人口は増え続けていて、2050年には98億人に達するとみられています。アジア地域を見ると、日本、中国、韓国では人口は減少に向かいますが、東南アジアでは今後も人口が増え続けます。
人口が減っている国が増えている国の人たちの力を借りて経済を支えていく。これは極めて自然な流れです。というより、それ以外の選択肢はありません。海外諸国を見ると、移民が増えている国は確実に経済が伸びています。今後は人材獲得競争が世界的に激化していくでしょう。「外国人を受け入れるか否か」といった上から目線の議論をしていたのでは、外国人は来てくれません。「日本に来たい」「日本に来てよかった」と言われる国にならなければならないのです。
外国人の採用にはメリットしかない
──企業でも人材難が顕在化しつつあります。
誰もが知っているような有名大手企業でも、採用に苦労していると耳にします。中小企業はいよいよ人集めが深刻な問題になっていくでしょう。
しかし、それは日本人だけに目を向けているからです。日本人の就職率は98%に達していますが、外国人の就職率は40%未満です。つまり、日本で働きたいのに働けない外国人が非常に多いということです。これは企業から見れば、外国人をターゲットにすることで人材獲得が容易になることを意味します。企業は外国人採用を本気で検討すべきだと思います。
 |
──人手不足の解消以外に、外国人を採用することのメリットにはどのようなものがありますか。
GTNは190人の社員中、140人が外国人です。国籍は19カ国に及び、皆、3言語以上を当たり前に話します。中には、6言語を使える社員もいます。海外の有名大学を卒業している社員も少なくありません。
ここまでダイバーシティが進むと、日々の仕事は気づきの連続になります。社員から「こんなサービスがあったらいいな」というアイデアが次々に出てきて、それが事業につながることもあります。また、海外にビジネスを広げていく場合にも、外国人社員がいるかいないかで、展開は全く異なるでしょう。外国人社員がたくさんいれば、世界の市場に関する知見を日常的に吸収することができます。日本人社員の目も、おのずと世界に向くことになるでしょう。
今後、国内市場が縮小していく中で、日本企業は海外に販路を求めていくしかありません。そのグローバル時代にあって、外国人の採用にはメリットしかない。そう言っていいのではないでしょうか。
──これまで外国人採用の経験がない企業へのアドバイスをいただけますか。
最初はどの会社でも苦労すると思います。しかし、それは採用される外国人の方も同じです。「郷に入りては郷に従う」ことが外国人には当然求められますが、会社の方も文化の違いなどを理解しなければなりません。お互いに相手の気持ちになって歩み寄ること。それがまず何よりも大事だと思います。
その次に大切なのは、人事制度の仕組みを変えることです。GTNでは評価のブラックボックスをなくし、すべてオープンにしました。それぞれの社員のコンピテンシーを他の社員が評価し、それを定量化してポイント化する。ポイントが一定数に達すれば自動的に昇格できる。主任になりたい人はプレゼンテーションをして、チームの3分の2以上の支持があれば主任になれる──。そんな仕組みです。
しかし、私たちは海外の企業のようになることをめざしているわけではありません。社内公用語は日本語であり、大切にしているのは「家族」「絆」といった日本的経営を支えてきた理念です。日本の文化や価値観は外国人にも間違いなく通用します。「家族」「絆」という理念を前面に掲げてから、当社の離職率は50%から7%まで減りました。日本の文化や技術力と外国人の能力をうまくミックスすることができれば、日本はまだまだ世界で戦える。そう私は信じています。
 |
東京の中でも特に外国人が多い街の1つである池袋にGTM本社はあります。そのオフィスで取材と撮影をさせていただきました。特に印象的だったのは、社内のミーティングルームが鮮やかに彩られ、社員の皆さんがいきいきと働いている光景でした。社員の7割以上は外国人。まさに多様性が会社に活気をもたらしている好例を見せていただいた気持ちです。後藤社長と話して驚いたのは、人口動態をはじめとする様々な数字が完璧に頭にインプットされていること。その数字を基に語られるビジョンには大いに説得力がありました。日本全体のダイバーシティに向けて、これからもご活躍ください。