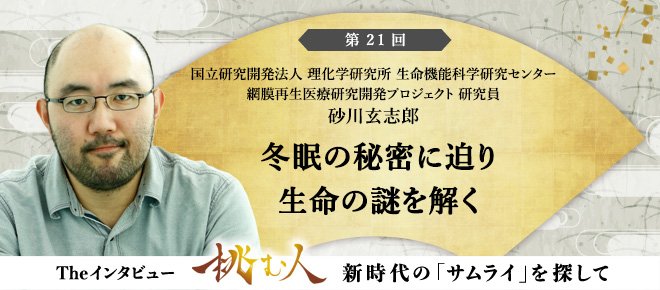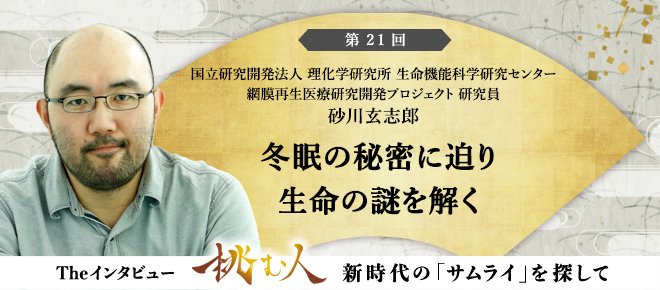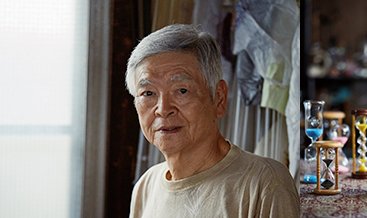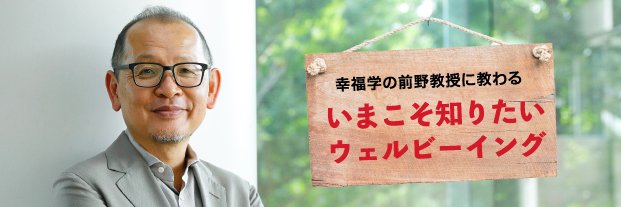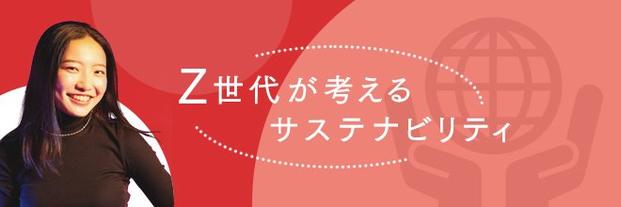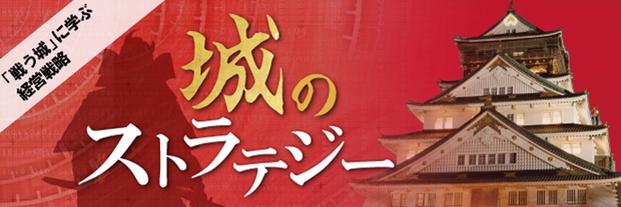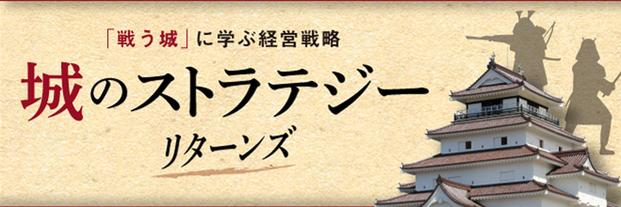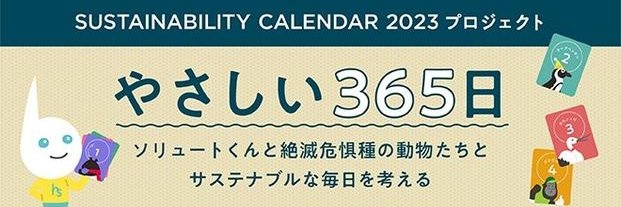※本記事は2020年9月に掲載されたものです
生命活動にとって最も大事なものは何か
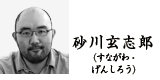 国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト 研究員 |
※黒字= 砂川玄志郎 氏
──動物が冬眠するメカニズムについて教えていただけますか。
実はよく分かっていないんです。体温が下がって動かなくなるのが冬眠の一般的なイメージだと思いますが、実は体温が下がるから冬眠するのではなくて、基礎代謝が落ちて、動かなくなるから、結果的に体温が下がるわけです。
哺乳類の体温は、通常は37℃プラスマイナス2℃から3℃の間に保たれています。普通はここから体温が極端に下がると命が危険にさらされます。人間の場合、体温が32℃か31℃になると心臓の動きが鈍り、30℃を切った状態が長時間続くと死に至ります。
しかし冬眠動物は、4℃から5℃くらいの体温で数カ月間生きることができます。ここには何かトリックがあるはずです。代謝が下がるだけでなく、低い温度で生きられる仕組みが隠されているはずです。しかし、それが何かはまだ分かっていません。
 |
──変温動物も冬眠しますよね。
カエル、ヘビ、魚、それから昆虫にも冬越えをする種がいます。これも正確なメカニズムは分かっていないんです。変温動物は体温が下がると体が動かなくなるので、その延長線上に冬眠があるともいわれています。しかし、カメの中には、代謝の仕組みが冬眠中に変わる種類もいます。そのメカニズムが哺乳類と同じなのかどうか。それも判明していません。
──冬眠する動物とそうでない動物の差はどこから生まれるのでしょうか。
最後の氷河期が終わったのが今から2万年ほど前です。2万年前にはすべての動物が冬眠をしていたのではないか。その後気候が徐々に温暖になるにしたがって、冬眠をしないという選択をする種が増えてきた。そんな説があります。
現在の肉食動物は一般的には冬眠しません。気候が温暖になってくれば冬でも歩き回ることができるので、冬眠している他の動物を食べてしまえばいい。一方、草食動物の場合、温暖になったといっても食料となる植物は冬にはほとんど枯れてしまいますから、春になるまで空腹に耐えなければなりません。だから、代謝を落として空腹に耐えられる状態、つまり冬眠を選択し続けた。そう考えることも可能です。冬眠状態になれば、敵に襲われるリスクは増えます。それでもその戦略の方が生存の可能性が高かったということなのかもしれません。
──雪山で遭難した人が低体温の状態で生き延びたという例も国内外でいくつか報告されているようですね。
あれも一種の冬眠かもしれません。僕は、人間の中にも遺伝的に冬眠可能な人がいるのではないかと考えています。例えば、冬眠に必要な100の因子があって、そのうちの一つでも欠けると冬眠できないが、たまたまそれを失っていない人がいる。そんな可能性があると思うんです。その因子が何かが分かれば、人為的に冬眠状態を引き起こせるはずです。
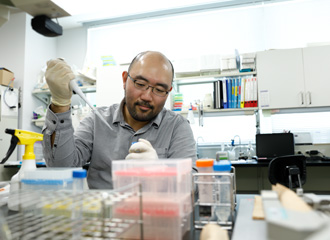 |
──代謝を落としても生き延びることができるのはなぜなのでしょうか。
そこが冬眠研究の大きなポイントです。冬眠中の動物の身体の酸素使用量は、場合によっては通常の1%くらいまで落ちます。つまり、呼吸の回数を100分の1にしても生きられるということです。では、その1%の酸素は何に使われているのか。それが明らかになれば、代謝をぎりぎりまで落としてもなお犠牲にできない機能が何か、つまり、生命活動にとって最も大事なものが何かが分かるはずです。
──なるほど。冬眠の研究とは、生命活動における「絶対」とは何かを明らかにすることであるともいえそうですね。
僕たちは生命の現象には、生と死の2つの状態しかないと考えていますが、実はその間に、死に最大限近づきながら、そこからリカバリーできる状態があるということです。そこでどのような生命活動が成立しているのか。それが明らかになれば、従来の生命観が書き換えられる可能性もあると考えています。
重症患者を救う時間を確保するための「冬眠」
 |
──どのようなきっかけで冬眠研究の道に進んだのでしょうか。
僕はもともと小児科医で、1年半ほど大阪赤十字病院の小児科で働いてから、救急病棟に移り、さらに重症の子どもを治療する国立成育医療研究センターの手術集中治療部で勤務しました。そこには全国から重い病気がある子どもが運ばれてくるのですが、あまりに重症の場合は、救急車での移動中に命を落とす恐れがあり、搬送さえできないこともあります。
それをどうにかして救うことができないかと考えていました。
そんな時、冬眠するキツネザルがいるという論文をたまたま読んだんです。冬眠といっても、そのサルが生息しているのは冬のないマダガスカル島で、乾期で木の実などが採れなくなる時期に冬眠と同じ状態になるということでした。サルが冬眠する例があるのなら、同じ霊長類の人間も冬眠できるのではないか。そう僕は考えました。それで人工冬眠の研究をすべく、すぐに大学院入学の勉強を始めたわけです。
──重症の患者を救うことと冬眠がどう結びつくのでしょうか。
冬眠とは代謝が極端に落ちた状態です。その状態を人為的に引き起こすことができれば、いろいろな病気の進行を止めることが可能になります。例えば、心筋梗塞など血流が滞ることで命が危険になる病気があります。一般に、梗塞状態になって30分以上過ぎると死ぬ可能性が高くなるといわれているのですが、臓器の代謝を落とせば、ある程度の時間、血液から酸素を得る量が極端に少なくなっても命を永らえることができます。それによって病院にたどり着く時間を稼げれば、命を救うことができるし、低酸素状態による脳へのダメージを防いで、後遺症を回避することもできます。
──いわば、酸素や栄養の「需要側」の機能をいったん低下させるわけですね。
まさしくその通りです。これまで急病の際は、血圧を上げる、酸素を投与する、輸血をするといった「供給側」の機能を補完する治療法がすべてでした。それでも亡くなってしまう人はいます。しかし、それに「需要側」の機能を抑制する治療を組み合わせれば、命を助けられる確率は格段に高まるはずです。
人工冬眠の技術が宇宙進出を後押しする
──人工冬眠の研究は現在どのくらいまで進んでいるのですか。
冬眠研究の最大のハードルは、「冬眠動物は年に1度しか冬眠しない」ということです。いつでも冬眠させることができれば研究も進むのですが、これまではほぼ不可能でした。マウスには「日内休眠」という現象があって、24時間餌を与えないと、動かなくなって体温が下がります。これは冬眠に似た状態ではあるのですが、体温は20℃台までしか下がりませんし、数時間しか続きません。
しかし最近になって、マウスの脳のある部位を刺激すると冬眠状態に導くことができる可能性があることが分かりました。この現象は、日内休眠をしない大型のネズミであるラットでも確認されました。これは大きな発見です。なぜなら、異なる動物の間で同じ現象が起きるということは、哺乳類に広く保存されている機能である可能性があるからです。
今後、任意に冬眠状態をつくり出すことができれば、その間に体の中の低代謝の仕組みを調べることが可能になるでしょう。さらに、いろいろな細胞に変化させることができるiPS細胞を使うことによって、その成果を人に応用できる可能性も見えてくるはずです。今僕が描いているのはそんなシナリオです。
──そのような基礎研究が進めば、臨床現場への応用の道筋も見えてきそうですね。
患者さんを助けたいという思いから始めた研究ですから、最終的には臨床に活かしていきたいですね。人工冬眠治療が普通にできるようになれば、脳障害による後遺症が減るので、寝たきり状態の人が少なくなり、健康寿命も延びることになります。それによって、超高齢社会の課題である医療費を抑制することも可能になると思います。
──医学以外にも応用の可能性はありそうですか。
可能性があるのは宇宙分野です。地球から火星に行くまでに、最短でも1年半ほどかかります。つまり、ロケットに1年半分の食料や酸素を積み込まなければならないということです。しかし、代謝を10%まで落とすことができれば、食料や酸素も10分の1で済みます。人工冬眠は、人類が宇宙進出をめざすに当たって非常に重要な技術になるはずです。
もう少し発想を広げてみると、僕が「人生の再配分」と呼んでいる考え方もあり得ます。例えば、おじいちゃんが孫の結婚式にどうしても出席したいが、寿命から見て恐らく不可能である。そんな場合にしばらく冬眠して寿命を延ばす、つまり、人生の時間の配分を変えるという考え方です。
さらに未来には、いつでも自由に冬眠ができる「念ずれば冬眠」が実現する可能性もあると僕は考えています。心筋梗塞になった瞬間に自ら冬眠するという選択をすれば、病院に搬送される時間を稼ぐことができ、自分の命を自分で永らえることができます。修行を積んだヨガ行者の中には、自分の意思で代謝を極端に落とすことができる人がいます。だから決して夢物語ではないと思っています。
 |
人工島である神戸市の港島に医療関係の研究機関が集められたのは、阪神淡路大震災の後だったそうです。そのような機関の一つ、理化学研究所生命機能科学研究センターでインタビューと取材をさせていただきました。冬眠研究は日本ではあまり進んでおらず、この領域に特化した研究者も数えるほどしかいないとのこと。その一人である砂川さんですが、研究している人が少ないからこそ「自分が冬眠の謎を解き明かしてやる」という情熱に溢れていると感じました。その情熱をもって、生命の神秘をぜひ解き明かしてください。