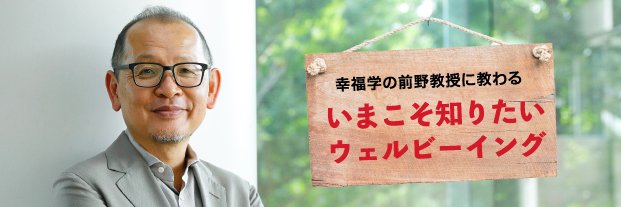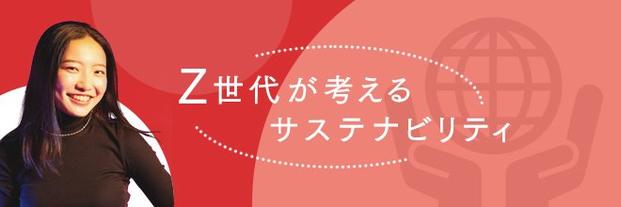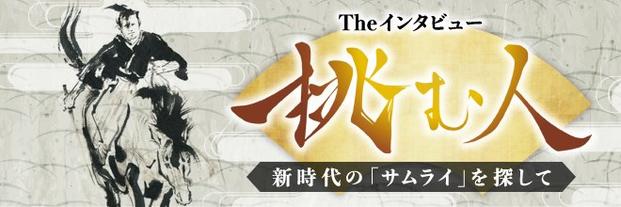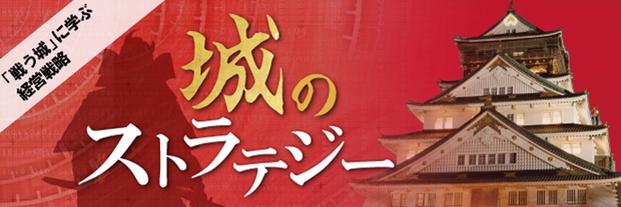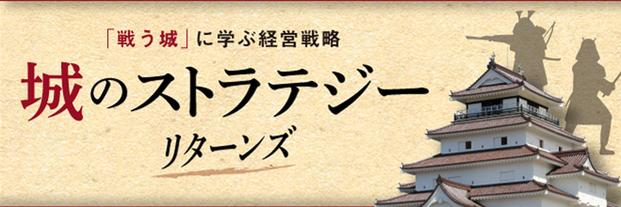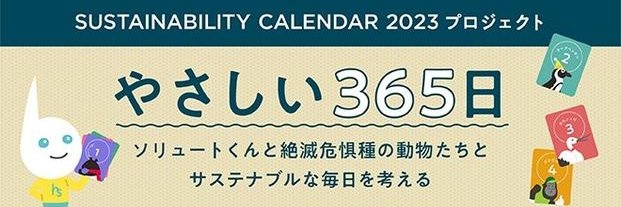※本記事は2022年3月に掲載されたものです

著書『渋沢栄一100の訓言』、他多数。
変化から一歩も二歩も先行できたのはイノベーションの力
私たちが生きている現代は、インターネットやAIなどのテクノロジーの発達によって、社会が激変している時代といってよいでしょう。
渋沢栄一が青年期を過ごした幕末から江戸時代もまた、第2次産業革命によって鉄鋼の生産という新しいテクノロジーが発達した時代でした。鉄道が普及して大量の物資や人員を陸路で一気に移動できるようになり、また電気や化学などの分野でも技術革新が進みました。
そんな時代に渋沢栄一が、世の中の変化から一歩も二歩も先んじて生き抜くことができたのは、彼が持つイノベーションの力だったと私は思います。
イノベーションを引き出す「"と"の力」
渋沢栄一のイノベーション力は、『論語と算盤』という言葉そのものに込められています。当時の人の多くは、この言葉を耳にして、「論語=道徳」と「算盤=経済」を両立させるのは無理な話だと感じたことでしょう。しかし、渋沢栄一はこの2つを「と」で結びつけました。どちらも活かす「"と"の力」が重要だと考えたのです。
そもそも、イノベーションは無から生じることはほとんどありません。多くの場合、世の中にすでに存在しているものを、うまく組み合わせることで生まれると私は考えています。別々に存在しているものを、「"と"の力」で組み合わせることで、新しい価値をつくるのがイノベーションだと思うのです。
とはいえ、誰もが思いつく組み合わせでは、新しいものは生まれません。重要なのは、一見関係なさそうに見えるものを合わせる点にあります。「と」で結ばれた2つのものに矛盾があるように見えても、そこで諦めることなく、忍耐強く試行錯誤を繰り返すことが大切です。
するとある時、「この視点ならば、うまくフィットするぞ!」というひらめきが訪れるかもしれません。このひらめきこそが、イノベーション誕生の瞬間です。最初から、「そんなのは無理」と決めつけて思考が停止するようでは、残念ながら「"と"の力」が足りません。
「"と"の力」と対照的なのが、「"か"の力」です。「論語か算盤」ならば、それは2つのうちの1つを選ぶことを示します。ゼロか1か、勝ちか負けかをはっきりさせる考え方です。もちろん、この発想も重要です。二者択一することで効率性や生産性の向上、物事の厳密な分析ができるようになるためです。企業活動には、この「"か"の力」が欠かせません。
しかし、「"か"の力」には限界があります。それは、すでに存在しているものを見比べて進めているだけなので、そこから新しいイノベーションが生まれることはないためです。
カレーうどんに象徴される「"と"の力」の価値
「論語と算盤を組み合わせるなんて、渋沢栄一のような特別な人だからできたのではないか」
そう言われるかもしれません。しかし、日本人は伝統的に「"と"の力」の感性が豊かだと私は感じています。そのいい例が、カレーうどんです。うどんは大昔に中国大陸から日本に入ってきましたが、カレーは近代になってやってきた料理です。日本人はその2つの異国から発祥した食べ物をどうしたかというと、「カレー"と"うどん」を同じ鍋に入れてしまったのです。おまけに出汁まで入れてしまいました。それが本当においしい!カレーうどんは、「"と"の力」がもたらした優れたイノベーションだと思います。
もし、「カレー"か"うどん」のままならば、それぞれの品質が向上することはあっても、カレーうどんのようなイノベーションは起こらなかったでしょう。
B級グルメから一流の高級料理まで、日本は世界一食事がおいしいといわれるのも、食材に関して余計な壁を設けることなく、「"と"の力」で組み合わせてきたからではないでしょうか。
もっとも、料理は例外かもしれません。日本の多くの業界では、異質なものを組み合わせようとしても、さまざまな規制や壁が設けられていて、なかなか「"と"の力」を発揮できないでいます。たとえ壁がなくても、あると思い込んで自己規制してしまいがちです。
これが、1990年以降の日本の姿ではないでしょうか。30年にわたって「失われた時代」と呼ばれてきましたが、失われたのは時代ではなく、日本人の自信・自尊です。自分にはできそうもない、やってはいけないんだと萎縮してしまい、枠に押し込まれているようにも見えます。そんな状態では、イノベーションは生まれません。
AIにもまねできないイマジネーションの力
「"と"の力」には、もう一つ大きな働きがあります。それは、今ある現実から飛躍して、その飛躍した状態と現実をつなげるイマジネーション力です。
生物学者に聞いた話ですが、イマジネーションというのは、地球上の生物で私たち人間だけに与えられた能力だそうです。チンパンジーやゴリラは人間に近い生物といわれますが、彼らは現実にいるところにしか「自分」はありません。
これに対して人間は、どんなに遠い場所にでも、過去にでも未来にでも、想像の力によって飛躍できます。そして、その飛躍した状態と現実をつなげることができるのです。人類だけが野生の群れの状態から抜け出し、集落をつくり、村や町、都会という文明を築き上げたのも、イマジネーションの力による部分が大きいのではないでしょうか。
イマジネーションは、AIにもまねができません。AIは、インプットされたデータをすべて保存して、忘れることなく、「"か"の力」で分析を猛スピードで行います。つまり、デジタルの0と1による分析を軸として、目前の出来事を一つひとつ予測して、それをひたすら繰り返していくだけです。AIには、関係のなさそうなものをいきなり組み合わせたり、現実から飛躍してつなげたりすることはできません。
「"と"の力」は、チンパンジーもAIも持ち合わせていない、まさに人間力そのものなのです。
渋沢栄一がいう『論語と算盤』の神髄は、「"と"の力」がもたらすイノベーションであり、人間力そのものです。時代環境がいかに変化しようとも、イノベーションの力があれば時代に先んじることができる。そして、その積み重ねこそが人類の歴史であり、サステナビリティの基本でもあるということを、『論語と算盤』は私に教えてくれるのです。
次回は、コロナ禍を超えて日本と日本企業が持続可能な発展をするために、とるべき方向性について考えていきます。