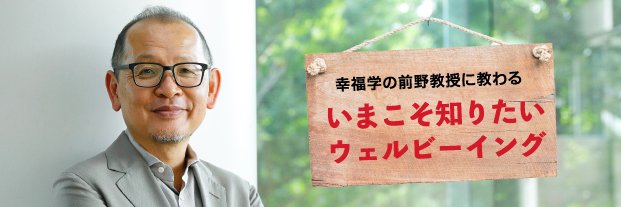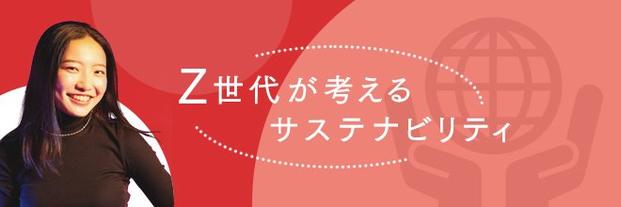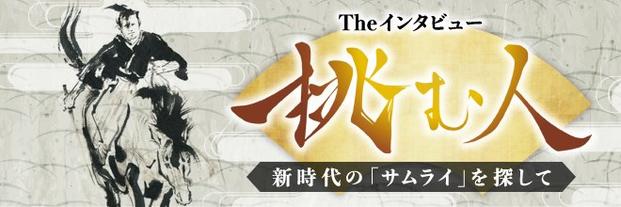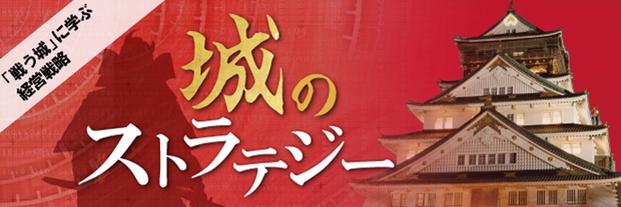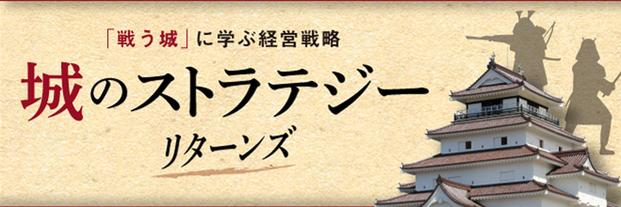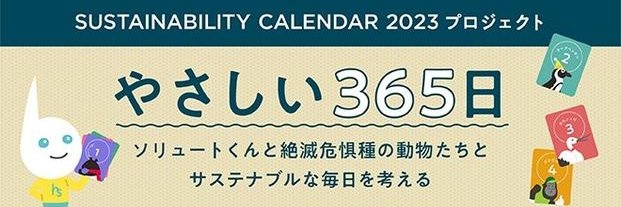※本記事は2022年5月に掲載されたものです

著書『渋沢栄一100の訓言』、他多数。
今の日本を見て、渋沢栄一は嘆き、怒るはず
もし、現代に渋沢栄一が生きていたら、日本の社会や経済を見て「正しい道理はどこに行ったのだ」と嘆き、大いに怒っていることでしょう。
『論語と算盤』の「ただ王道あるのみ」という一節に、次のような記述があります。
「法の制定されているのはよいが、法が制定されておるからといっても、一も二もなくそれに裁断を仰ぐということは、なるべくせんようにしたい」
ルールの範囲内で動いていれば問題ない、ルールさえ破らなければいいという考え方に対して、渋沢栄一は異議を唱えたのです。ルールばかりを意識して思考停止になることなく、何が正しいかをきちんと自分の頭で考えて行動しなさいというのが、渋沢栄一のいう「道理」だと私は理解しています。
教育についても一家言をもっていた渋沢栄一
渋沢栄一の説く「道理」は、まさに今の日本に必要なことだと思います。何が正しいかを自分の頭で考えることをせず、ルールの前で思考停止になってしまうのが多くの日本人の姿ではないでしょうか。
その根本原因は日本の教育にあると私は考えます。日本の今の教育は、なにが正解でなにが不正解かというハウツーのスキルアップばかりが重要視され、「なぜ?」という疑問を発する訓練をしてきませんでした。
とくに私が育った昭和時代はそうでした。戦後でリセットされた日本では、先進国の大量消費を満たすための大量生産が必要となり、恒常的に質の高いものを比較的安価に生産することで日本は大繁盛しました。教育現場でもそうした労働市場の求めに応じて、一定の規格に合った人たちをどんどんつくりだしたのです。
確かに当時はそれでよかったのですが、今では通用しません。競合国が増えて日本のシェアが奪われ、大量生産では世の中が豊かになれないことを日本人自身も気づいてきました。
こうした状況を打破するには、「そもそも、なぜこれをするのか?」「なぜ勉強するのか?」「なぜ働くのか?」という根源的な問いを自分自身に発して、自分なりの答えを求めていける教育が不可欠です。大きく時代が動いている中で、教育だけが旧態依然でいいわけがありません。
「時代の変化に教育が追いついているのか?」
実は、こう述べたのは渋沢栄一その人です。明治末から大正になって物質的には豊かになったが、はたして精神的に追いついているのかと栄一は疑問を呈していました。時代を引っ張る優秀な人材を輩出させるのではなく、100人が100人同じレベルの人材を出すような教育に対して、皮肉を込めて批判しています。
まさに現代の日本と似た状況だったのです。もし栄一が生きていたら、現在の教育のあり方に対して怒っていたに違いありません。
ビニールハウスで思考停止してしまった30年間
栄一が怒りそうなのは教育だけではありません。現代日本人の考え方や働き方を見たら、大いに怒ることは疑いありません。
栄一は、「現在の状態に満足することは衰退のはじまりだ」という言葉を残しています。これはまさに現在の日本にあてはまるのではないでしょうか。デフレだ、不況だといいながらも、私たちはそこそこ楽な生活ができています。もちろん格差の問題は深刻で、新常態では貧困層などの生活に大きな課題があることは承知しています。しかし、世界全体の水準と比較すれば、豊かに暮らしていける部類に含まれるのは間違いありません。
いわば、ビニールハウスのような生暖かい環境に、私たちは満足してしまっているのです。そして、何も考えずにぬくぬくとしているうちに30年が経ってしまい、気がついたら日本は新興国に追いつかれ、業態によっては追い抜かれてしまいました。
では、そこで日本人が思いなおしたかというと、そんなことはありません。時代が変わっても思考停止のまま、自分たちだけが日々平和に過ごしていければいいと考えている人が、相変わらず多いのではないでしょうか。そんな様子を見たら、渋沢栄一は心底怒ることでしょう。もちろん、豊かな生活を求めるのは人間として当然のことですが、現状に満足していたら衰退する一方です。
ビニールハウスの中で思考停止していたのは企業も同様です。私が所属していた金融業界では、ここ30年間というもの、国民の現預金残高が積み上がる一方で、言われたとおりにやっていれば良いという思考が委縮する「コンプライアンス不況」に陥っていました。それぞれの方々は、きちんと仕事をしたという自負はあるでしょうが、結果として今のようになっているのは、ぬるま湯で満足して自分の頭で考えてこなかったことに原因があると思います。
日本企業が「変わる」ために使ってはいけない3つのフレーズ
では、激変する時代において、企業はどう変わるべきなのでしょうか。その答えは業界によって違いますし、具体的な方針を私が示すことはできません。しかし、これだけはアドバイスできます。それは、たった3つのフレーズを日本の組織から排除することです。次に挙げる3つのフレーズを、会社、役所、大学などの組織から排除できれば、日本が再び上向く時代を取り戻せることに間違いありません。
1つ目は「前例がない」というフレーズです。よく耳にしますが、変わりたいのなら絶対に使ってはいけません。前例のないことに取り組むのが、変わるということです。これまでの延長線上では変わることはできません。前例を崩した上で、また新しい前例をつくるべきなのです。
2つ目のフレーズは「それは組織では通りません」というフレーズ。「私はいいと思うんですが、上がウンといってくれないでしょう」というのも同じです。もし、その人が当事者として「これはダメです」というのなら理解できます。その人の職務として自ら判断しているからです。しかし、自分はいいけれども組織が通してくれないというのは、その人が自らの職務を放棄していることにほかなりません。
3つ目は「誰が責任取るんだ」というフレーズです。これもおかしな言葉であって、責任を取るのは当事者であり、あるいは直属の上司であり、社長に決まっています。ほかに誰が責任を取るのでしょうか。
この3つのフレーズこそ、思考停止を示す明らかな証拠です。過去30年間、私はこうしたフレーズをいろいろな立場の人から、さまざまな場面で聞かされてきました。しかし、黙っていても右肩上がりだった昭和の時代ならいざ知らず、令和の時代には通用しません。これからの時代に合う環境を企業が整えようとするならば、絶対に追放すべき言葉です。
最終回となる次回は、本当の意味でのサステナビリティを実現するために、各世代の企業人が心にとめておくべきことを考えます。