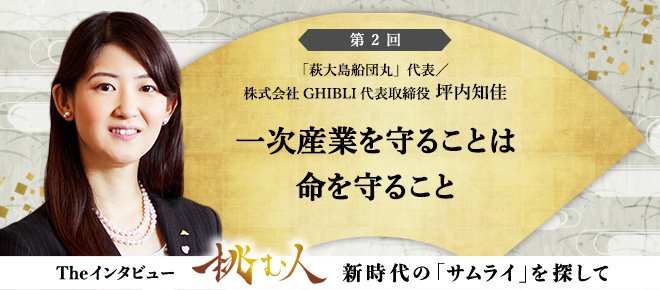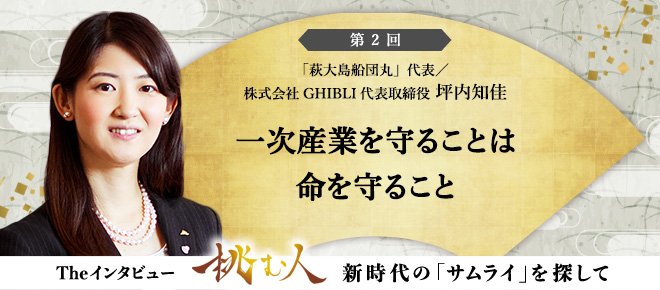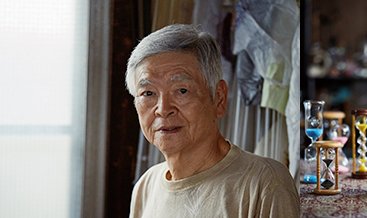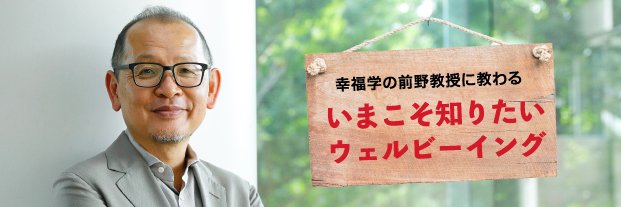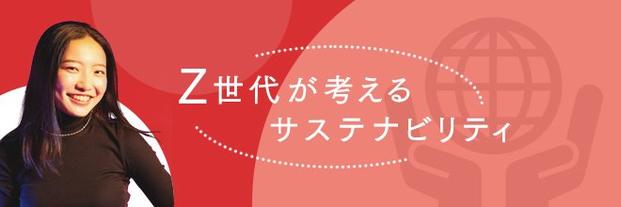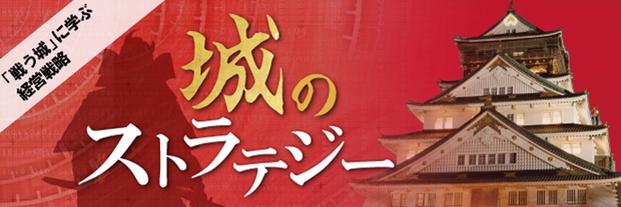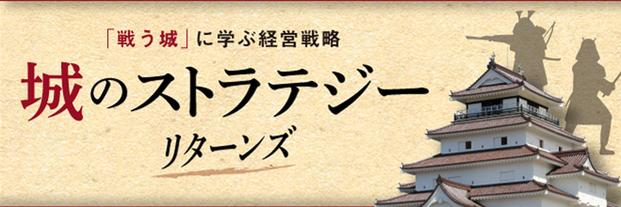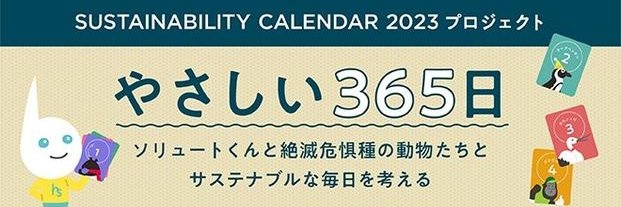※本記事は2019年6月に掲載されたものです
熱量を注げば注いだ分の成果は必ず出る
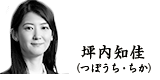 「萩大島船団丸」代表/株式会社GHIBLI代表取締役 |
漁業との出合いは23歳の時だった。山口県萩市で生活することになったのは、結婚相手の勤務地だったからだ。20歳で結婚。21歳で男子を出産したが、数年後に離婚した。シングルマザーとなって、持ち前の英語力やパソコン力を活かし、観光協会の翻訳の仕事を得た。
今に至る大きな転機となったのは、協会からの依頼で年末の繁忙期に旅館のコンサルティングを請け負ったことだ。実際には宴会現場での仲居指導だったその仕事で出会ったのが、萩市から船で25分ほどの沖合にある萩大島の漁師、長岡秀洋氏だった。
「忘年会を2日間手伝ったのですが、そのどちらにも長岡がいたんです。この辺りでは見ない顔だね、どこの子? そう話しかけてきたのが最初でした」
坪内知佳氏は「運命の出会い」をそのように振り返る。萩大島の漁師を束ねる存在であったその長岡氏が、「地元の漁業復興に力を貸してほしい」と坪内氏に持ちかけてきたのはそれからひと月後のことだった。
日本の漁獲量は、1984年をピークに減少を続けている。2017年度水産白書によれば、日本の2016年の水揚げ量は全盛期のおよそ3分の1で、世界8位となっている。「漁業大国」の面影はもはや昔日のものというわけだ。坪内氏が長岡氏と出会った2010年の頃、萩においても漁獲量の減少は大きな問題となっていた。
坪内氏にもとより漁業に関する知識があったわけではない。それでも長岡氏の唐突な依頼を引き受けたのは、漁業が「命に直結する仕事」であると直感したからだった。
「できませんでした」は絶対にありえない
19歳の時に悪性リンパ腫で余命半年と宣告された。死に直面した経験は、彼女の中の何かを大きく変えた。
「再検査で別の病気だと分かって宣告は取り消されたのですが、それ以来、命と食の結びつきを強く感じるようになりました。漁業や農業などの一次産業は、たくさんの人に食を提供する仕事ですよね。いい魚を届けることは人々の命を支えることになる。そう考えて長岡の話に乗りました」
 |
坪内氏が考えたのは、漁業の六次産業化である。生産(一次)・加工(二次)・販売(三次)の一貫モデルである六次産業の仕組みをつくることができれば、自分たちが取った新鮮な魚を全国の消費者に直接届けることができるし、漁業者の利幅も大きくなる。
「魚が取れないこと自体は資源管理の問題ですから、私たちがすぐにどうするわけにもいきません。しかし、漁師たちの生活を守るには、その条件の中で漁業経営を成り立たせなければならないわけですよね。だったら、それが可能な仕組みを考えるしかありません」
そうして生まれたのが、朝に取れた魚を箱に詰め、宅配便で東京などの消費地の顧客のもとに届ける「鮮魚BOX」だった。農林水産省の六次産業化支援プログラムの認定第1号事業となったこのモデルが、萩における「漁業革命」の第一歩となった。
むろん、簡単に成立するビジネスではなかった。それまで加工、販売を手がけてきた事業者を通さないモデルである。一方の漁業者の側にも、エンドユーザーである消費者のために魚を取るという思考はゼロであった。漁業関係各方面との間に起きた激しい衝突は、著書『荒くれ漁師をたばねる力』に詳しい。
その衝突を乗り越えて、ビジネスを軌道に乗せることができたのは、「計画は必達でなければならない」という坪内氏の強い信念があったからである。
「農水省に事業計画を提出した段階で、何カ月後までに何件成約させるか、1年先はどうか、2年先はどうなるかをすべて決めています。"できる"と思って計画を立てているわけですから、"できませんでした"はあり得ないんですよ。計画したことを実現するのは当然のこと。そう私は思っています」
11年に坪内氏を代表、長岡氏を船団長とする「萩大島船団丸」を旗揚げし、14年には株式会社GHIBLI(ギブリ)を設立した。現在の事業の柱は「鮮魚BOX」をはじめとする直販事業のほか、コンサルティング事業、真珠の販売事業、萩への視察旅行を企画・運営する旅行事業の4本だ。売り上げはそれぞれ25%ずつと、きれいなポートフォリオを描いている。
とりわけ注目すべきは、六次産業化の取り組みの経験をもとにしたコンサルティング事業だ。萩大島の漁師自身がコンサルタントとして各地の漁業関係者のもとに赴く画期的なモデルである。坪内氏は説明する。

川崎市「ヴォラーミ ジュエルスタジオ」の藤巻今朝男氏。坪内氏が産地から仕入れた真珠は、ここで加工されて販売されている
|
「漁業は認可事業で、勝手に海に出てはいけないことになっています。萩大島の漁師は年に60日から70日しか稼働することができません。だから以前は、年のうち300日はぶらぶらしているしかなかったんです。そこで、漁に出ない日は、各地の漁業関係者のもとに足を運び、自分たちの経験を伝えて漁業復興のお手伝いをする事業を立ち上げました。この取り組みを始めてから、はっきり分かりましたね。全国の産地が抱えている課題は100%同じだって」
漁獲高の減少、人手不足、産業構造の問題─。それらを解決するために、自分たちの経験知を他の産地に提供する。これによって、これまで全くつながりのなかった異なる産地の漁師間にネットワークが生まれるというメリットもある。
「私が産地に行っても、"あんたに何が分かる"と言われる場面でも、何十年もの間、大きな漁船に乗って魚を取ってきたベテラン漁師が行くと、みんな神妙に話を聞くんですよ」
そう言って坪内氏は笑う。
8年間で大きく変わった人々のマインド
平坦な人生ではなかった。高校時代の夢はキャビンアテンダントになることで、オーストラリアに留学し、大学も外国語学科に進学したが、先述の病気のためにその夢をあきらめなければならなかった。時期を同じくして、実家の家業がうまくいかなくなった。萩に嫁ぎ大学を中退したが、その結婚生活が長続きしなかったことも先述の通りだ。
「19歳の時が人生の底でしたね。あれ以下の底はないですから、仕事で大変なことがあってもどうということはありません」
決して楽ではない漁という仕事で人々の食を支えているにもかかわらず、それに関わる人たちが補助金なしでは生活ができないのが日本の漁業の実情だ。それをおかしいと感じるのは「人として当たり前のこと」だと坪内氏は言う。その「当たり前のこと」を大きな声で発信し続けてきた8年間だった。
この8年で萩の雰囲気が大きく変わったことを実感しているという。「明治維新発祥の地」という地元の人たちのプライドは、よそ者を拒む閉鎖性につながっていた。しかし、全国から視察者や観光客が頻繁に訪れることで、少なくともこの事業に関わる漁業関係者のマインドは以前とは比べものにならないくらいオープンになった。以前は船に乗って魚を取ること以外に何の興味も示さなかった漁師たちは、現在では視察ツアーや観光ツアーに訪れた人々を自ら案内し、もてなすようになっている。「熱量を注げば、注いだ分の成果は必ず出る」と坪内氏は言う。
現在の計画は、47都道府県のすべてに自社の拠点をつくって、全国の産地とつながることだ。視線は漁業だけではなく、日本の一次産業全体に向けられている。いずれ「一次産業サミット」を開催したいと話す。
「農業にも漁業にもシーズンがありますよね。だったら、閑散期に他の生産現場に働きに行けばいいんですよ。一次産業のワークシェアリングができれば、人手不足の問題はかなり解消されるはずです」
個人的なビジョンは「死ぬまでこのままで生きていくこと」だ。本当に好きなことをやっている。だから、無理をしているわけでもないし、苦労もない。
「でも、死ぬまで仕事を続けるには、エネルギーを残しておかなければなりませんよね。60%、70%の力で淡々と働いていきたいと思っています」
その60%の力が常人の200%の力に匹敵してしまう。海の男たちと渡り合ってこられたのは、そのパワーがあったからだ。まだ32歳。一次産業を、そして人々の命を守る戦いはこれからも続く。
 |
坪内さんが現在力を注いでいる事業の一つが、真珠の六次産業化です。その事業をサポートする神奈川県川崎市のジュエリー工房「ヴォラーミ ジュエルスタジオ」でインタビューと撮影を行いました。産地から仕入れた真珠をこの工房で加工して製品化し、販売しているとのことでした。毎日のように日本全国を飛び回っている坪内さんにお時間をいただけたのはとてもラッキーでした。マスコミに登場される機会も多い方ですが、その人生観やビジネス観を直接うかがって、まさに生きる力をいただいたと感じました。これからも日本の漁業、農業を力強く支えていってください。