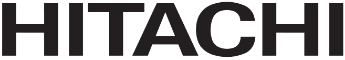
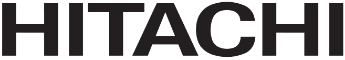
日立ソリューションズが提供する、デジタルマーケティングを実施するうえで役に立つコラムや基礎知識やトレンド解説などをご紹介します。
製造業のビジネス加速に役立つ最新情報をご紹介します。
社内外の識者によるビジネスコラムや最新のITトレンド解説などを掲載します。ぜひご活用ください。
ビジネス加速に役立つ最新情報を紹介します。
社内外の有識者によるビジネスコラムや最新のトレンド情報などを掲載します。
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
建設業界におけるICTのトレンドや建設テック、i-Construction…をキーワードに、関連する知識や将来展望など、当社のエンジニアがわかり易く解説・紹介します。
今、本当に必要なセキュリティ対策は何かー
セキュリティ関連の最新話題の情報についてご紹介します。
セキュリティリスクを回避するために、企業では、どのような対策が必要なのでしょうか。「ランサムウェア」「情報漏洩」「テレワーク」にまつわるコラムをご紹介。
IDaaSのグローバルNo.1サービス「Okta」の、日本国内初のディストリビュターである日立ソリューションズが、IDaaSの役立つ情報をお届けします。
ビジネスデータを活用し、新しい時代を切り拓いていくすべてのビジネスパーソンのために、ビジネスコラムやお悩み解決策、業界の動向など、さまざまなお役立ち情報を提供しています。
日立ソリューションズのセキュリティアナリストが独自の視点でセキュリティ情報をお届けします。
日立ソリューションズ提供の地理情報システムに関する空間情報活用コラムを掲載。ビジネスで地理情報システムを活用する際に役に立つ基礎知識や、将来の展望などをやさしく紹介します。
法改正や人事経営課題のトレンドなど、人事労務に関わる最新テーマを中心に情報を配信しています。人事労務管理や戦略的人財マネジメントのヒントや情報収集に、ぜひご覧ください。
日立ソリューションズが提供するRPAに関するお役立ち情報。
RPAを活用するうえで役に立つ、コラムや基礎知識、トレンド解説などをご紹介。ぜひご活用ください。
勤怠管理や労務管理に関する課題解決策や、テレワークの推進、働き方改革など、人事業務に関わるの皆様のお役に立つ情報をご紹介します。
ワークライフシナジーを創出し、個人の幸せとともに企業の成長を実現するためのヒントをご紹介します。