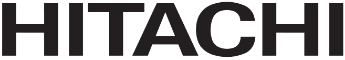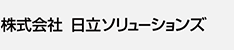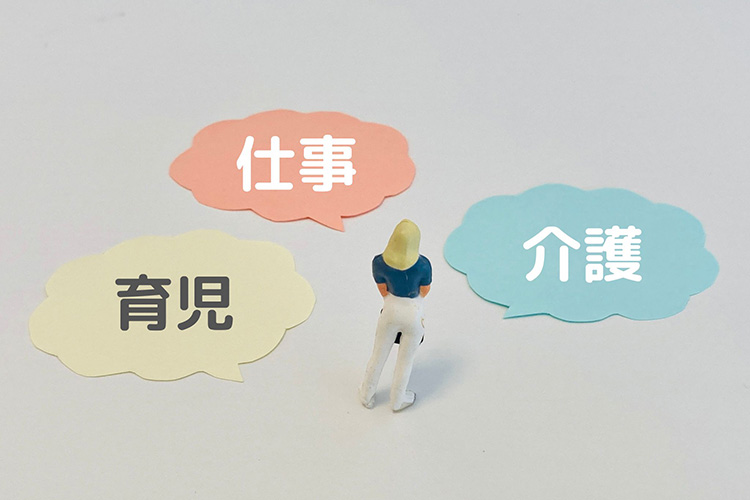お役立ち情報
勤怠管理とは?目的やシステム導入の必要性についてわかりやすく解説

勤怠管理システム「リシテア」より勤怠管理・労務管理のお役立ち情報のご紹介です。
勤怠管理とは、従業員の出退勤や労働時間、休暇状況を正確に把握することで、法令遵守や適正な給与計算を支える重要な業務です。近年、働き方改革により、労働時間の記録や時間外労働の上限規制が義務化され、企業にはより厳密な勤怠管理が求められています。リモートワークの普及などもあり、従来の方法では対応が難しくなり、その重要性がさらに高まっています。
本記事は、勤怠管理の目的や重要性、さらに勤怠管理システム導入の必要性や選び方などについて詳しく解説します。
「リシテア 勤怠管理ソリューション」のサービス資料をダウンロード
目次
勤怠管理とは
勤怠管理とは、企業が従業員の出勤・退勤、休憩、休日などの勤務状況を正確に把握し、労働時間を管理することです。企業には労働基準法に基づき、従業員の労働時間を適正に把握し、法定労働時間(1日8時間、週40時間)や休憩時間などの規定を遵守する責務があります。使用者である企業は、労働時間の適正な把握を行うため、労働時間だけでなく、労働日ごとの始業時刻や終業時刻を記録する必要があります。
勤怠管理の目的
勤怠管理は労働基準法に定められた企業の義務であり、労働安全衛生法の改正により2019年4月から客観的な記録による労働時間の把握も義務付けられています。
では、勤怠管理はどのような目的で行われるものなのでしょうか。勤怠管理の主な目的を4つ紹介します。
賃金を正しく支払う
勤怠管理の第一の目的は、正確な賃金を支払うことです。賃金は、労働者の労働時間をもとに計算されるため、始業時刻や休憩時間、終業時刻だけでなく、時間外労働や休日労働なども正確に把握する必要があります。これができていなければ、正しい賃金計算はできません。
もし賃金を正しく計算せず、割増賃金が支払われない場合、従業員との信頼関係を損なう可能性があります。さらに、割増賃金の未払いが原因でトラブルが発生すれば、企業の社会的信用にも悪影響を及ぼします。従業員が安心して働ける環境を提供するためは、適切な勤怠管理が不可欠です。
労働時間を管理し長時間労働を是正する
働き方改革により労働基準法が改正され、36協定を締結した場合でも時間外労働の上限時間は、原則として月45時間、年360時間に規定されました。また、36協定の特別条項で認められる時間外労働についても細かな基準が設定されており、法に違反した場合には罰則を科せられる恐れがあります。
勤怠管理による毎日の始業時刻や終業時刻、休憩時間などの正確な把握は、長時間労働の防止につながるものです。
有給休暇の取得状況を把握する
6カ月以上継続して勤務し、労働日の8割以上を出勤した従業員には、有給休暇が付与されます。また、2019年4月の働き方改革関連法の法改正により、有給休暇が10日以上付与される従業員には、付与された日から1年以内に最低5日分の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられています。
さらに、有給休暇の日数は継続勤務年数や週の所定労働日数によって変動します。そのため、適切な有給休暇の付与と取得状況を管理するためには、勤怠管理が重要です。
コンプライアンスを遵守する
勤怠管理を適切に行わなければ、時間外労働の正確な把握や割増賃金の正しい計算ができません。また、有給休暇の取得状況も確認できなくなるため、勤怠管理を怠ると法律違反につながる可能性があります。
さらに、労働基準関係法令に違反した企業は、厚生労働省によって公表されます。法令違反が明らかになれば、社会的信用を失い、事業の運営にも大きな悪影響を与える恐れがあります。そのため、労働基準法や労働安全衛生法などの法律を遵守するためにも、勤怠管理は欠かせない取り組みです。
勤怠管理の対象企業・従業員
勤怠管理が必要になるのは、労働基準法に示されている労働時間の規定が適用されるすべての事業場です。したがって、農業や水産業を除くほとんどの企業には、規模を問わず勤怠管理の義務があります。
また、以前は、勤怠管理の対象となる従業員は労働基準法第41条に定める者(管理監督者)およびみなし労働時間制が適用される従業員を除くすべての従業員とされていました。しかし、2019年4月の労働安全衛生法の改正により、管理監督者についても労働時間の状況を把握することが企業に義務付けられました。この改正により、管理監督者も労働時間の記録や健康管理の観点から適切な対応が求められるようになりました。
勤怠管理の管理項目
勤怠管理を適切に行うためには、労働時間や休日、有給休暇など、さまざまな項目を正確に把握する必要があります。以下では、勤怠管理において法令で定められている管理項目について詳しく解説します。
始業・終業時刻、休憩時間
始業時刻と終業時刻、休憩時間がわからなければ、正確な労働時間は把握できません。厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の中で、勤怠管理を行ううえで管理が必要な項目として記しています。
また、労働基準法では休憩時間についても定められており、労働時間が6時間以上8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩が必要です。また、それぞれの時間は1分単位で算定しなければなりません。
出典:厚生労働省Webサイト(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)
時間外・休日・深夜労働時間
時間外労働や休日労働、深夜労働については、割増賃金の支給対象となります。それぞれ賃金の割増率が異なり、月60時間を超える時間外労働についてはさらに割増賃金率が引きあがります。適正な賃金計算や長時間労働を避けるためにも、勤怠管理によって時間外・休日・深夜労働時間を正確に把握する必要があります。
出典:厚生労働省Webサイト(しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編)
勤務日・休日
勤怠管理では、勤務日や休日も把握し、労働した日数を把握しなければなりません。労働基準法では、休日についても規定がなされており、企業は従業員に対し、少なくとも1週間に1日以上、または4週間に4日以上の休日を与えなければならないのです。休日出勤があった場合には、振替休日または代休を取得できているかの確認も必要になります。
有給休暇取得日数・残日数
有給休暇の取得日数や残日数も管理が必要です。企業には従業員に対し、有給休暇を取得させる義務を負っています。そのため、有給休暇の取得が進んでいるか取得状況と残日数を確認し、必要に応じて有給休暇を取得するよう従業員に働きかけなければなりません。有給休暇の取得義務に違反した場合、労働基準法違反となるため罰則を科せられる恐れがあります。
出典:厚生労働省Webサイト(年5日の年次有給休暇の確実な取得)
勤怠管理の代表的な方法
勤怠管理に必要な項目について紹介してきましたが、実際、勤怠管理を行う際にはどのような方法で行えばよいのでしょうか。勤怠管理の代表的な方法とその特徴を紹介します。
従来からある勤怠管理の方法は、紙の出勤簿に手書きで勤怠情報を書き込む、または打刻式のタイムカードを使用する方法です。いずれも低コストで手軽に勤怠を管理できるというメリットがありますが、紙の勤怠管理は不正申告の恐れもあります。また、タイムカードの場合、タイムレコーダーへの打刻漏れが生じやすく、また人数が増えてくると転記ミスが発生しやすいといったリスクを考慮しなければなりません。
勤怠は原則として客観的な記録による把握が義務付けられています。そのため、自己申告制を採用している場合には、パソコンの使用時間と申告している労働時間に著しい乖離がある場合は実態調査を実施し、労働時間の補正を行わなければならないなどの対応が必要です。
参考:厚生労働省Webサイト(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)
表計算ソフトによる勤怠管理
表計算ソフトを使い、勤怠管理を行う方法もあります。始業時刻や終業時刻、休憩時間、有給休暇の取得などを入力し、割増賃金などを自動計算する関数を用いて勤務表を作成すれば、コストをかけずに勤怠管理が可能です。
しかし、従業員自身が入力を行うため、入力ミスや不正な申告が起こる可能性があります。また、自己申告になるため、紙やタイムカードでの管理と同様に客観的な記録となりません。そのため、表計算ソフトの勤怠管理においてもパソコンのログイン・ログアウト時間などと照合し、入力された時間が正しいものであるかチェックする必要があります。
参考:厚生労働省Webサイト(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)
勤怠管理システムによる勤怠管理
スマートフォンやパソコンと連携させ、始業時刻から終業時刻、時間外労働、有給休暇の取得状況まで一括で管理できるシステムを活用した勤怠管理の方法です。時間外労働時間の集計も自動で行えるため、管理の手間を軽減し、給与計算のミスも発生しにくくなります。また、法改正にもスムーズに対応できる点もメリットです。
しかしながら、導入するシステムによっては機能を使いこなすまでに時間がかかるケースもあるため注意が必要でしょう。
勤怠管理システムの導入メリット
客観的なデータで出退勤時間を管理し、正しく勤怠管理を行うためには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムの導入によって得られる主なメリットを紹介します。
正確な給与計算ができる
勤怠管理システムでは、出退勤の情報から、給与計算で必要な時間外労働時間や深夜労働時間、休日労働時間などを自動計算することが可能です。手計算の場合、時間外労働時間などの集計や賃金の割増率の計算の際にミスが生じる場合もあるでしょう。しかし、勤怠管理システムであれば時間外労働時間なども自動で計算されるため、給与システムとの連携により、正確な勤怠データに基づいた給与計算が行えるほか、源泉徴収額や社会保険料などの計算ミスも防げます。
労働時間を適正に管理できる
勤怠管理システムでは、パソコンやスマートフォンなどさまざまな方法を用いて、出退勤時間をリアルタイムで正確に管理できます。紙やexcelの勤怠管理に比べ、記入や転記のミス、不正申告、データの不正改ざんのリスクも抑えられるでしょう。また、勤務情報をタイムリーに把握できるため、長時間労働の抑制や適正な労働時間の管理、有給休暇の取得推進にもつなげられ、コンプライアンス遵守の徹底にも役立ちます。
業務効率が上がる
有給休暇や休日出勤の申請・承認機能があればワークフローの自動化が可能になり、勤務状況から過剰労働や有給休暇の取得が進んでいない従業員を自動的に予測しアラートを通知する機能を活用すれば、労務管理の負担をさらに軽減できるでしょう。また、勤怠管理システムと給与計算システムを連携すると給与計算の省力化を図れます。勤怠管理システムの導入により、さまざまな面において業務効率の改善が可能になれば、人件費の削減も期待できます。
法改正にスムーズに対応できる
法改正がなされれば、その都度新たな法律に基づき、従業員の勤怠管理を行わなければなりません。
勤怠管理システムの場合、システムの設定を変更することで、新たな制度に対応することが可能です。また、クラウド型の勤怠管理システムであれば、法改正に合わせ、自動アップデートにより企業側の対応が不要なケースもあります。勤怠管理システムの導入は、法改正時の担当者の負担軽減とともに法令を遵守した運用を可能にします。
データを人事戦略に活用
勤怠管理システムの中には、収集した従業員の労働時間に関する情報を分析し、グラフなどをダッシュボードに表して可視化できるものもあります。有給休暇の取得率が低い部署がある場合、マネジメント体制を適切な形に改める必要があるでしょう。また、特定の部署に時間外労働が集中しているようであれば、業務量に対して人材が不足している可能性が高く、人材配置を見直したり、新たな人材採用を検討するなど、勤怠データを人事戦略に活用することも可能です。
勤怠管理システムの選び方のポイント
現在、さまざまな勤怠管理システムが提供されています。そのため、どの勤怠管理システムを選ぶべきか判断に悩むケースもあるでしょう。ここでは、勤怠管理システムの導入にあたり事前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
自社に合った機能を満たしているか
勤怠管理システムは、まず、自社の業界・勤務形態に合ったシステムや打刻方式でなければなりません。シフト制やフレックスタイム制、時短勤務、リモートワークの対応、また、PC・スマートフォンからのWeb打刻、icカードにも対応したカードリーダー打刻、GPSを活用した打刻方法など、自社に必要な機能を備えているかを確認しましょう。
操作性も導入前に確認しておきたいポイントです。自社が求める機能が搭載されているかに加え、実際に使用画面を見て使いやすさも確認することをおすすめします。
ほかのシステムと連携できるか
勤怠管理で得られる情報は、給与計算や労務管理、人事評価など、さまざまな業務で活用されます。そのため、勤怠管理システムがほかのシステムと連携できない場合、システムへのデータ入力を手作業で行う必要があり、大きな手間がかかってしまいます。せっかく勤怠管理システムを導入しても、ほかのシステムと連携できなければ、業務効率の向上が十分に実現できません。
勤怠管理システムを選ぶ際には、ほかのシステムとの間でスムーズにデータの連携ができるものを選ぶことが大切です。
効果に見合った納得できる価格か
勤怠管理システムを導入する際には、コストがかかります。クラウドサービスの場合は月額料金が必要になり、オンプレミス製品の場合はライセンス数に応じた初期費用、保守費用が必要になるケースが一般的です。
コストの総額を把握することも大切ですが、価格だけを基準にシステムを選ぶと必要な機能が揃っておらず、導入後に満足できる効果を得られない可能性があります。導入時にはコストと導入によって得られる効果のバランスを考えることが大切です。
セキュリティ面に問題がないか
勤怠管理システムでは、従業員の個人情報を取り扱います。したがって、セキュリティ体制に不備があり、不正アクセスによって情報が漏洩した場合は大きな問題に発展する恐れがあります。また、マルウェアの感染によりシステム自体が利用できなくなったり、データが消失するリスクも出てきます。
暗号化や不正アクセス防止など、セキュリティ機能が十分に備わっているかも重要なチェックポイントです。
サポート体制が充実しているか
システム導入時には初期設定が必要なため、設定方法について相談できる体制があれば安心です。また、システム運用中にもわからないことやトラブルが発生する可能性があるでしょう。そのような場合に迅速にサポートを受けられなければ、処理に時間がかかり、業務にも支障が生じます。
導入時や導入後に、どのようなサポートを受けられるのか、サポート体制についても事前にしっかり確認するようにしましょう。
導入実績・事例が豊富か
勤怠管理システムを導入する際には、導入実績もチェックすべきポイントです。豊富な導入実績を持つシステムほど、長年にわたるさまざまな企業での導入事例をもとに改良を重ねているケースが多いため、初期トラブルなどの発生リスクを抑えられます。また、多様な業種や規模の企業に対応した豊富な事例をもとに、さまざまな知見を生かして、自社の制度やニーズに最適化された提案を受けることができます。
システム導入前には、これまでの導入実績や事例などについて確認することも忘れないようにしましょう。
クラウド型かオンプレミス型か
勤怠管理システムには、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。クラウド型は、比較的導入費用を安く抑えられ、自動アップデート機能によって法改正に対する対応が不要となるといったメリットがあります。一方、オンプレミス型は導入時のコストが高くなりますが、自社に合わせたカスタマイズや高度なセキュリティ環境の構築が可能です。勤怠管理システムの導入を検討する際には、自社の状況に合わせ、適切なタイプを選ぶようにしましょう。
関連記事:オンプレミス型とクラウド型の違いとは?メリット・デメリットを解説
日立ソリューションズが提供する「リシテア」は、オンプレミス型とクラウド型からニーズに合わせて、適したスタイルを選べる勤怠管理システムです。1700社以上の導入実績を生かし、さまざまな勤務形態や打刻法に対応しており、柔軟な運用が可能です。
実績豊富な勤怠管理システム「リシテア」の詳細はこちらからご確認いただけます。
まとめ
適切な勤怠管理を行うことは企業にとって法的な義務であり、客観的な記録による労働時間の正確な把握が求められている今、勤怠管理システムの活用が非常に有効です。勤怠管理システムを導入することで、労働時間を正確に把握できるだけでなく、業務効率の向上やコンプライアンス遵守にもつながります。
勤怠管理システムを導入する際には、価格と機能のバランスを十分に検討し、自社のニーズに適したシステムを選ぶことが重要です。また、サポート体制の充実度や過去の導入実績なども確認しながら、デモ画面などを実際に操作して使用感を確かめることをおすすめします。
何かご相談などありましたらお気軽に当社まで お問い合わせください。
記事公開日:2025年6月13日
「リシテア 勤怠管理ソリューション」のサービス資料をダウンロード
関連コラム

みなし残業(固定残業)とは?企業が知るべき違法になるケースや導入メリットを解説
勤怠管理
2025年10月6日
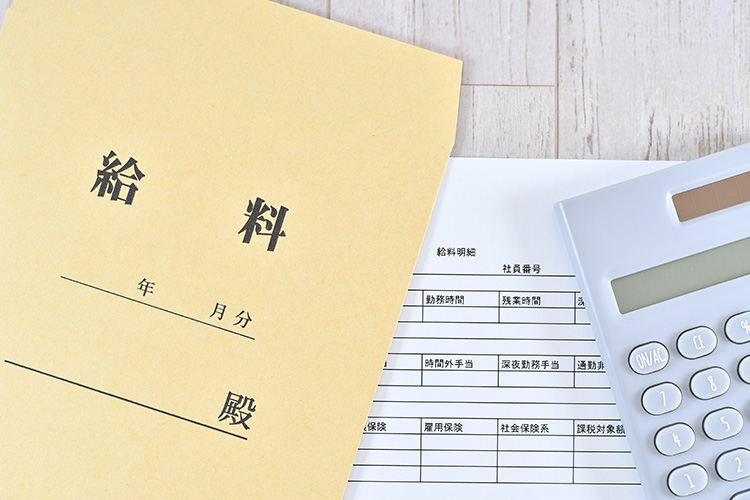
裁量労働制で残業代は発生する?計算方法と注意点を解説
勤怠管理
2025年10月6日
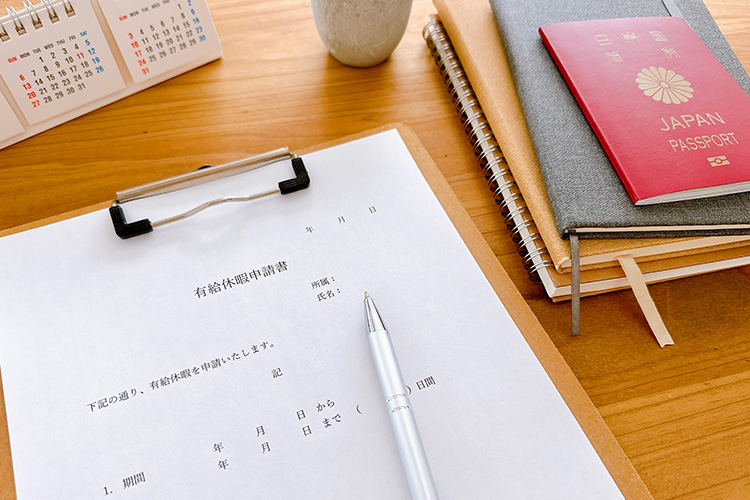
有給休暇の年5日取得の義務とは?付与日の計算や取得を促す方法を解説
勤怠管理
2025年10月6日

36協定とは?残業時間の上限や届け出の手順をわかりやすく解説
管理勤怠
2025年10月6日

残業時間の上限規制とは?年間・月間の上限や36協定について解説
勤怠管理
2025年7月9日

子の看護等休暇とは?2025年4月法改正に伴う変更や取得条件を解説
勤怠管理
2025年7月9日

リシテア 勤怠管理ソリューション
サービスの特長がわかる【事例付き】資料2点セット