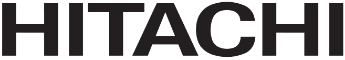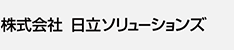お役立ち情報
【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法とは?改正ポイントや求められる企業の対応を解説
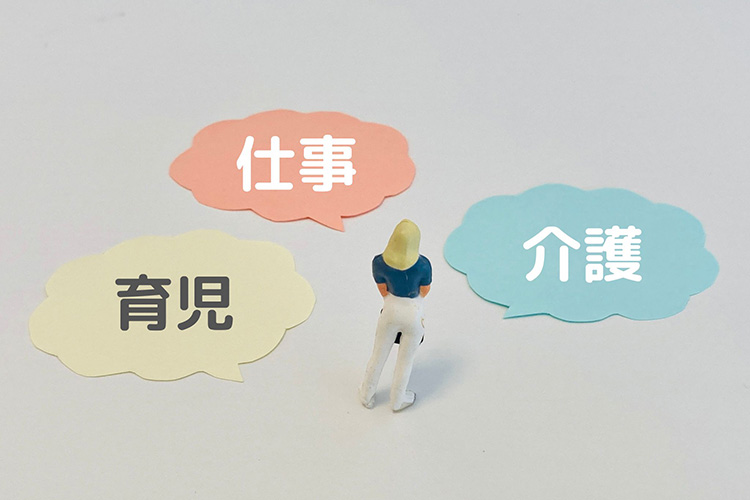
勤怠管理システム「リシテア」より勤怠管理・労務管理のお役立ち情報のご紹介です。
育児・介護休業法の改正により、男女が仕事と育児・介護を両立できるよう新たなルールが段階的に施行されます。2025年4月および10月に施行が予定されているこの改正では、柔軟な働き方や介護離職防止を目的とした新たな措置が盛り込まれています。しかし、改正内容や企業が取るべき対応について十分に理解できず、悩む労務管理者もいるかもしれません。
この記事では、2025年施行の育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の改正内容やポイントを解説し、企業が法改正に向けて準備すべき事項について詳しく説明します。
「リシテア 勤怠管理ソリューション」のサービス資料をダウンロード
目次
2025年施行の育児・介護休業法改正とは
2024年5月、育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の改正法が国会で可決・成立しました。男女ともに、仕事と育児・介護を両立できるような環境を作ることが目的です。
今回改正された項目は以下のとおりです。ほとんどの改正案は、2025年4月1日から施行されます。
| 改正事項 | 施行開始日 |
|---|---|
| 1.子の看護休暇の見直し | 2025年4月1日から施行 |
| 2.所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大 | |
| 3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | |
| 4.育児のためのテレワーク導入 | |
| 5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | |
| 6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | |
| 7.介護離職防止のための雇用環境整備 | |
| 8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認など | |
| 9.介護のためのテレワーク導入 | |
| 10.柔軟な働き方を実現するための措置など | 2025年10月1日から施行 |
| 11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 |
2025年に段階的に施行される育児・介護休業法改正のポイント
2025年に段階的に施行される育児・介護休業法改正では、男女が仕事と育児・介護を両立できる環境を整えるためのルールが新たに定められました。子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を可能にする措置の拡充や、介護離職防止のための環境整備、個別周知や意向確認の義務化などが盛り込まれています。ここでは、それぞれの改正ポイントについて詳しく解説します。
①子の看護休暇の拡大
子の看護休暇は、負傷や病気の子どもの世話をするために取得できる休暇です。対象となる子を養育する労働者は、1年度当たり5日(子が2人以上の場合は10日)を上限として取得できます。
今回の改正では、看護休暇がより多くの労働者に利用しやすくなるよう変更されました。主なポイントは以下のとおりです。
- 「子の看護休暇」の名称を「子の看護等休暇」に変更
- 学級閉鎖や子どもの行事への参加時にも看護休暇を取得可能
- 看護休暇対象となる子どもの範囲が、小学校就学前から小学校3年生修了まで拡大
- 雇用期間6カ月未満の労働者も看護休暇取得対象から除外できなくなる
②残業免除の対象範囲拡大
一定年齢までの子どもを養育する労働者は、企業に請求することで所定労働時間を超える残業が免除されます。これまでは3歳未満の子どもを養育する労働者が対象でした。
今回の改正では、残業免除の対象範囲が拡大され、小学校就学前までの子どもを養育する労働者も対象となりました。
③時短勤務の代替措置にテレワーク追加
企業は、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して短時間勤務措置を提供する義務があります。ただし、労使協定を締結することで短時間勤務制度の適用除外とすることが可能です。短時間勤務制度の適用除外となる対象は以下のとおりです。
- 雇用期間が1年未満
- 週所定労働日数が2日以下
- 業務内容や勤務体制上、短時間勤務制度が適用困難と認められる場合
その場合、フルタイム勤務が認められる代わりに代替措置が必要です。代替措置として認められるものは以下のとおりです。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- 始業時刻の変更(フレックスタイム制や時差出勤)
- 保育施設の設置運営またはそれに準ずるもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
- テレワーク ※今回の改正で新たに追加
④子育てをする労働者に対してテレワーク導入
今回の改正では、企業に対し、3歳未満の子どもを養育する労働者が育児休業を取得していない場合、テレワーク措置を講じることが努力義務として追加されました。努力義務であるため、テレワーク措置を講じなくても罰則はありませんが、企業には子育て中の労働者を支援する姿勢が求められています。
⑤従業員数300人超の企業に育児休業などの取得状況の公表の義務付け
従業員数1,000人超の企業には、2023年4月から男性労働者の育児休業取得率などの公表が義務付けられていました。これにより、毎年1回以上、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表する必要があります。
今回の改正では、この義務が従業員数300人超の企業にも拡大されました。公表時期は決算終了後3カ月以内で、インターネットなど一般に閲覧可能な方法で行う必要があります。厚生労働省は「両立支援のひろば」での公表を推奨しています。
この公表義務範囲の拡大により、より多くの企業で育児休業取得促進が期待されます。
出典:厚生労働省(両立支援のひろば)
⑥介護休暇の対象範囲拡大
介護休暇は、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休暇です。対象家族が1人の場合、1年度あたり5日が上限で、2人以上の場合は10日まで取得可能です。対象家族には以下が含まれます。
- 配偶者
- 父母
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 配偶者の父母
改正前は、週所定労働日数が2日以下や雇用期間6カ月未満の労働者は介護休暇取得対象外とされていました。しかし今回の改正により、入社6カ月未満の新入社員でも介護休暇を取得できるようになりました。
⑦介護離職防止に向けた雇用環境の整備の義務付け
今回の改正により、企業は介護休業や介護両立支援制度の円滑な利用を促進するため、介護に関する理解を深める環境整備を行うことが義務付けられました。具体的な取り組みとして以下の措置が示されています。
- 介護休業・介護両立支援制度などに関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度などに関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度などの利用事例の収集と提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度などの利用促進に関する方針の周知
これらの中から1つ以上を選択し、実施することが求められています。
⑧両立支援制度に対して個別の周知や意向確認の義務化
今回の改正では、介護に直面した労働者に対し、仕事と介護を両立するための支援制度について個別に周知し、利用促進を目的とした意向確認を行うことが義務化されました。具体的な周知内容は以下のとおりです。
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度などの内容
- 介護休業・介護両立支援制度などの申出先(例:人事部)
- 介護休業給付金に関すること
さらに、40歳を基準として、労働者が早い段階で制度への理解を深められるよう情報提供が求められています。情報提供期間は以下のいずれかです。
- 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)に属する年度(1年間)
- 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
情報提供時には、介護保険制度についても周知することが推奨されています。周知や意向確認は以下の方法で実施します。
- 面談(オンライン可)
- 書面交付
- 電子メール
- FAX
ただし、介護に直面した旨の申出をした労働者に対しては、メールとFAXは労働者自らが希望した場合のみ選択可能で、企業からは選択できません。厚生労働省では、周知や意向確認用ポスター例やリーフレット例を公開しています。
出典:厚生労働省(育児・介護休業等に関する規則の規定例)
出典:厚生労働省(介護保険制度について)
⑨家族を介護する労働者に対してのテレワーク措置
企業には、要介護状態にある家族を介護する労働者が介護休業を取得していない場合、テレワーク措置を講じる努力義務が課されました。これは子育て中の労働者へのテレワーク措置と同様であり、テレワーク措置を講じなくても罰則はありません。しかし、家族を介護する労働者への支援として企業には積極的な取り組みが期待されています。
⑩柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
企業には、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、職場のニーズを把握したうえで柔軟な働き方を可能にする措置を講じることが求められています。以下の5つの中から2つ以上を選択して実施し、労働者はその中から1つを選んで利用します。
- 始業時刻などの変更(フレックスタイム制や時差出勤)
- テレワーク(1日の所定労働時間を変更せず、月間10日以上取得可能なもの)
- 保育施設の設置運営またはそれに準ずるもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
- 養育両立支援休暇の付与(1日の所定労働時間を変更せず、年間10日以上取得可能なもの)
- 短時間勤務(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
企業が措置を選択する際には、過半数組合などから意見聴取の機会を設けることが必要です。
また、対象労働者への周知および意向確認を個別に実施することも義務付けられています。
周知時期や周知事項、周知・意向確認の方法は以下のとおりです。
| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで) |
|---|---|
| 周知事項 |
|
| 周知・意向確認の方法 |
|
当該措置に関する申出や実施、または労働者が伝えた意向を理由に不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。また、家庭や仕事の状況が変化する場合もあるため、上記時期以外にも定期的な面談が推奨されています。この改正は2025年10月より施行されます。
⑪働き方に対する個別の意向聴取と配慮の義務化
企業は、労働者が妊娠や出産などを申し出た際に、仕事と育児の両立について個別に意向確認を行い、その意向に配慮することが義務付けられました。
この際、企業は聴取した意向やその内容を理由として、労働者に不利益な取り扱いをしてはなりません。この改正も2025年10月より施行されます。
2025年4月施行の次世代育成支援対策推進法改正のポイント
次世代育成支援対策推進法は、自治体や企業による育児支援を定めた法律で、少子化対策の一環です。2025年4月施行の改正により、労働者の仕事と子育てに関する行動計画策定時における、状況把握や目標設定が義務化されました。また、今回の改正で法律の有効期限が延長されました。
①行動計画策定時における状況把握・数値目標設定の義務付け
今回の改正により、従業員数100人超の企業に対し、以下の実施が義務付けられました。
- 行動計画策定時の育児休業の取得状況や労働時間の把握
- 育児休業の取得状況や労働時間に関する数値目標の設定
少子化対策には、労働者による育児休業取得の促進と仕事と育児の両立が重要です。定量的な状況把握を通じて、育児休業取得促進をめざします。一方で、従業員数100人以下の企業については努力義務となっています。
②次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長
次世代育成支援対策推進法は、2005年4月から10年間有効な法律として施行され、2015年にも10年間延長されていました。しかし、少子化が加速している現状を受け、さらなる施策が必要と判断され、有効期限が再び10年間延長されました。
今回の延長により、有効期限は2035年3月31日までとなります。
出典:厚生労働省(新たな10年がスタート!次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定)
2025年施行の育児・介護休業法改正の目的
日本では少子高齢化が深刻化しており、労働人口の減少が懸念されています。2020年時点で28.6%だった65歳以上の割合を示す「高齢化率」は、2070年には約39%に達し、総人口は9000万人を下回ると予測されています。このため、育児や介護をしながら働ける環境づくりが急務となっています。また、厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」でも、仕事と育児や介護を両立するための課題が指摘されています。
これを受け、男性の育児参加を支援する体制整備が重要視されました。さらに、コロナ禍で普及したテレワークが育児・介護支援に有効な手段として注目され、今回の改正に盛り込まれました。
出典:厚生労働省(将来推計人口(令和5年推計)の概要)
出典:厚生労働省(今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書)
仕事と育児の両立
厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」によると、2023年度の育児休業取得率には、女性が84.1%である一方、男性は30.1%にとどまっています。しかし、前回調査(同11.2%)より 18.8 ポイント上昇しており、2023年4月改正の育児・介護休業法改正で企業に育休取得の意向の確認を義務付けたことや、10月施行の「産後パパ育休(出生時育児休業)」の影響が出ているとされています。それでもなお、女性と比べると男性の取得率には大きな差があります。
「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」では、現状の仕事と育児の両立支援に関するニーズが以下のように明らかになりました。
- 男性では、育児休業を利用していないものの、利用したかった人が約3割
- 女性は、子どもが3歳以降は短時間勤務を希望する一方で、子どもの成長に伴い残業をしない働き方や柔軟な働き方を求める傾向
- 障害児や医療的ケア児の場合、子どもの発達段階を年齢で区切ることが難しい など
この結果を受けて厚生労働省は、以下の対応が必要と判断し、今回の改正につながりました。
- 男性の育児休業のさらなる取得促進
- 小学校就学後も含めた、子の年齢に応じた残業をしない働き方や柔軟な働き方、休暇のニーズへの対応
- 障害や医療的なケアなど、多様な状況にある子や親に関するニーズへの対応
出典:厚生労働省(令和5年度雇用均等基本調査|厚生労働省)
出典:厚生労働省(今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書)
仕事と介護の両立
介護休業制度は家族の介護による離職を防ぐため1995年に創設されました。2016年には長期介護への対応として上限93日・3回まで分割取得可能や半日単位での介護休暇取得などが導入されました。
しかしながら、制度利用は進まず、依然として多くの人が介護を理由に離職しています。厚生労働省「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」では以下を課題とし、今回の改正へつながりました。
- 仕事と介護の両立支援制度の効果的な利用促進
- 介護に直面する労働者や職場の上司、企業の制度理解
出典:厚生労働省(今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書)
法改正に伴い企業が対応すべきこと
育児・介護休業法などの改正により、企業は社内規定の整備や労働者への周知といった対応を行う必要があります。これらの取り組みによって、労働者や管理職の理解が深まり、制度の利用促進につながります。以下では、それぞれの対応内容について詳しく解説します。
社内規定の整備
企業は、2025年4月までに就業規則を見直し、法改正に沿った規定へ追記・改定する必要があります。厚生労働省では、育児・介護休業に関する規定例や社内様式例を公開しており、これらを参考にすることが可能です。
どのような規定を作成すればよいかわからない場合や、具体的な例を確認したい場合は、厚生労働省が提供する規定例や社内様式例を活用するとよいでしょう。
出典:厚生労働省(育児・介護休業等に関する規則の規定例)
労働者への周知
制度の利用促進には、労働者への周知が不可欠です。新しい制度の内容や現行制度からの変更点など、法改正の主要ポイントを管理職も含めた全労働者に伝える必要があります。具体的な周知方法としては、メールや社内報、説明会の開催に加え、研修の実施も効果的です。
全階層の労働者に情報を共有することで、制度を利用しやすい職場環境を作ることが重要です。
就業環境の整備
就業環境の整備も、企業が対応すべき重要な課題の1つです。今回の改正により、柔軟な働き方を実現するための対応が義務化されました。残業免除の対象拡大や子の看護休暇の見直しにより、労働時間の短縮や休業取得者の増加が見込まれます。
その結果、現在の人員や配置では対応が難しくなる場合も考えられます。柔軟な働き方に対応するためには、自社の就業環境を整備する必要があります。具体的には、業務の役割分担を見直して属人化を防ぐ、人員配置を再検討する、さらには増員を検討するなど、業務体制全般を再考しましょう。
育児休業取得状況の公表準備
男性労働者の育児休業取得率などの公表が義務付けられた企業は、男性労働者の育児休業取得状況を把握し、公表内容や方法を事前に決めておいた方がよいでしょう。原則として、公表はインターネットなど一般の人が閲覧可能な方法で行うことが求められており、厚生労働省が推奨している「両立支援のひろば」を活用することが推奨されています。
公表は決算時期終了後おおむね3カ月以内に行うことが推奨されています。例えば、決算時期が2025年3月の場合、2025年6月30日が公表期限の目安となります。
出典:厚生労働省(両立支援のひろば)
「一般事業主行動計画」策定への対応
2025年4月1日以降、行動計画の策定・変更時には、育児休業の取得状況などの把握や数値目標の設定が義務付けられます。具体的には、男性労働者の「育児休業等取得率」または「育児目的休暇の取得率」、さらにフルタイム勤務の労働者の月ごとの法定時間外労働や休日労働時間数を把握する必要があります。これにより、企業は労働者の働き方や育児支援状況を正確に把握し、法律で求められる要件を満たした行動計画を策定することが必要となります。
出典:厚生労働省(新たな10年がスタート!次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定)
法改正に伴う勤怠管理への影響と対応
法改正により、仕事と育児・介護との両立支援が促進されることで、労働時間の短縮や休業取得者の増加が見込まれます。また、従業員数300名超の企業には育児休業取得状況の公表が義務付けられ、100名超の企業では育児休業の取得状況や法定時間外労働・休日労働時間数を把握する必要が生じています。これに伴い、法改正に沿った勤怠管理の見直しや、休業取得および労働時間の正確な把握が重要となっています。
こうした課題に対応するためには、勤怠管理システムの活用が有効です。勤怠管理システムを導入することで、休業取得率や労働時間を効率的に管理でき、法改正にも柔軟に対応可能です。
おすすめの勤怠管理システムとして「リシテア」が挙げられます。「リシテア」は労働時間や休暇管理はもちろん、モバイル端末での申請・承認機能やテレワーク勤務を導入している企業の勤務実態を正確に把握する機能を有しています。例えば、勤務場所登録やGPS打刻でテレワークの実施状況を把握することが可能であり、柔軟な働き方を支援します。法改正や新しい制度にも柔軟に対応できる勤怠管理システムをお探しの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
まとめ
2025年4月から、男女が仕事と育児・介護を両立できる環境を整えることを目的に、育児・介護休業法の改正が段階的に施行されます。子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を可能にする措置の拡充や、介護離職防止を目的とした環境整備、個別周知や意向確認の義務化などが新たに規定されました。
法改正により、企業には社内規程の見直しや労働者への周知、就業環境の整備など、多岐にわたる対応が求められます。また、育児休業取得状況の公表義務化に加え、行動計画策定時の状況把握や数値目標設定の義務化に伴い、労働者の労働時間や休業取得状況を一元管理する必要性も高まっています。これらへの対応には適切な管理体制の構築が不可欠です。
こうした課題への解決策として効果的なのが勤怠管理システムです。勤怠管理システムを活用することで、労働者ごとの労働時間や休業取得率を効率的に把握・管理できます。法改正への対応を円滑に進めるためにも、自社に最適なシステムの見直し・導入を検討することをおすすめします。
何かご相談などありましたらお気軽に当社まで お問い合わせください。
記事公開日:2025年6月13日
「リシテア 勤怠管理ソリューション」のサービス資料をダウンロード
関連コラム

みなし残業(固定残業)とは?企業が知るべき違法になるケースや導入メリットを解説
勤怠管理
2025年10月6日
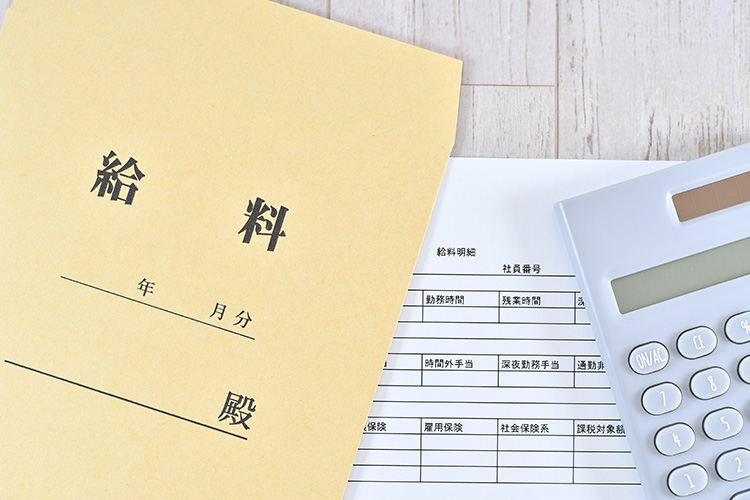
裁量労働制で残業代は発生する?計算方法と注意点を解説
勤怠管理
2025年10月6日
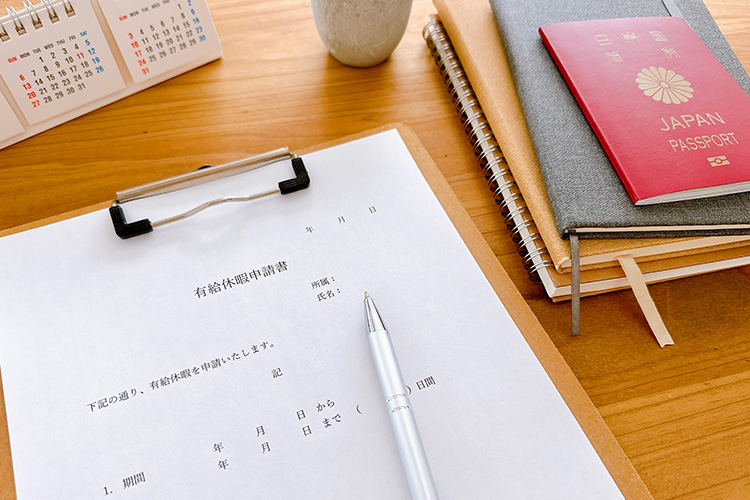
有給休暇の年5日取得の義務とは?付与日の計算や取得を促す方法を解説
勤怠管理
2025年10月6日

36協定とは?残業時間の上限や届け出の手順をわかりやすく解説
管理勤怠
2025年10月6日

残業時間の上限規制とは?年間・月間の上限や36協定について解説
勤怠管理
2025年7月9日

子の看護等休暇とは?2025年4月法改正に伴う変更や取得条件を解説
勤怠管理
2025年7月9日

リシテア 勤怠管理ソリューション
サービスの特長がわかる【事例付き】資料2点セット