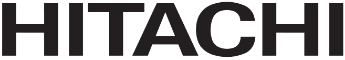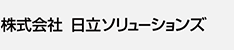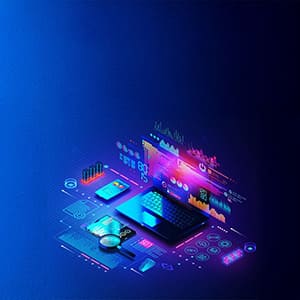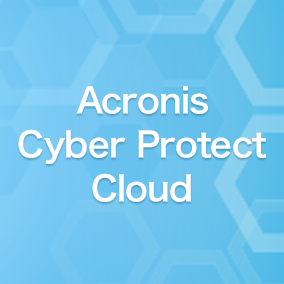ビジネスコラム
【専門家監修】ペーパーレスとは?ペーパーレス化を進めるために必要なこと・進め方を解説
記事公開日:2021年10月27日
記事更新日:2022年8月30日
リモートワークの普及やDX、SDGsなどの影響を受け、各企業で「ペーパーレス」への取り組みが求められています。ペーパーレス化は単純に「紙」を電子化するだけではなく、紙に関わるさまざまな業務の見直しや改善も併せて行う必要があります。
企業でペーパーレスを推進させていくためには、社内の業務規定やマニュアルなど、簡単にできるところから電子化していくことが重要です。
本記事では、ペーパーレス化を進めるために必要な業務や施策について解説します。
監修者

中川 克幸
株式会社 日立ソリューションズ
スマートライフソリューション事業部 ビジネスコラボレーション本部 マーケティング推進部
部長
セキュリティソリューションのSE・マーケティング活動を経て、現在は企業のDX推進につながるビジネスデータ活用の講演・提案などを中心に活動中。

「活文」を使った導入事例
活文なら、ビジネスデータの整理・管理からインサイトまで一括提供。
活文のサービスをご利用いただいたお客さまの導入事例をご紹介しております。
ペーパーレスとは

はじめに、ペーパーレスの目的とペーパーレスが普及した背景について解説します。
ペーパーレスの目的
ペーパーレスの主な目的は、オフィスから紙をなくして電子化を進め、以下のようなメリットを得ることです。
- 紙や印刷代などのコスト削減
- 文書管理の効率化
- 紙での承認フローをなくして決裁スピードを早める
- セキュリティの向上
企業内では、請求書や注文書、契約書類、会議資料など多くの文書が日々作成されています。これらの資料を紙に印刷して使用することも少なくありませんが、ペーパーレス化を進めることで、紙ではなくパソコンやタブレットなどの端末で閲覧できるようになります。そのほかにも、保管スペースの費用削減や業務の効率化、リモートワークなどの多様な働き方に対応しやすくなるといったメリットも得られるでしょう。
もともと文書を紙で印刷していた主な理由の一つとして、押印による承認や対応の必要性がありました。海外では署名(サイン)が一般的ですが、日本では請求書や契約書類などの社外向けの重要書類や、社内用の回覧、稟議書などの文書において押印する慣習が深く根付いています。
しかし、近年では、電子契約サービスの登場で押印不要の流れが生まれ、ペーパーレス推進の声が高まっています。
ペーパーレスが普及した背景
ペーパーレスが普及した背景には、電子帳簿保存法改正や、コロナ禍によるリモートワークの浸透などの影響もあります。
電子帳簿保存法改正は1998年に制定された法律ですが、時代に合わせて改正を重ねてきました。紙での保存が義務付けられていた国税関係帳簿書類の電子データでの保存承認や、メールや電子FAXでの取引情報の電子保存義務化など、改正を重ねるごとにペーパーレス化のニーズを高めています。
また、コロナ禍によって多くの人がリモートワークで仕事をするようになり、どこにいても書類の確認や資料を共有できる環境が必要となったことも、ペーパーレスが普及した要因の一つです。働き方が多様化するなか、これまでは「紙を使用した業務に慣れている」ことを理由にペーパーレス化を避けていた企業も、ペーパーレスの推進に力を入れるようになりました。
ペーパーレスを定着させるために必要なこと
ペーパーレスを定着させるためには、まずは社内の特定の業務からペーパーレスを定着させ、徐々に社内全体に浸透させていくことが重要です。
ここでは、ペーパーレスを定着させるために必要なことについて解説します。
社内文書の管理ルールや業務フローの整備
まずは、身近にある社内文書からペーパーレス化を進めていきましょう。
「ペーパーレス化を進めましょう」と呼びかけるよりも、具体的な管理ルールや業務フローを整備するやり方が有効です。たとえば日立ソリューションズでは、まず社員一人ひとりが紙の印刷を極力減らす、カラー印刷はしない、など「紙を出力しない」ことをルールとして定めています。
社内の業務規定・マニュアルなど簡単にできるところから電子化する
ペーパーレス化をある程度周知した段階で、業務規定やマニュアルなどのペーパーレス化を進めます。
ただし、社内の業務規定やマニュアルは紙での利用を前提としていることが多いため、一気にペーパーレス化を実施してしまうと業務に支障が出る恐れもあります。
まずは資料の回覧を紙ではなくPDFにするなど、簡単なことから始めていきましょう。
リモートワーク時のセキュリティ対策の強化
インターネットを経由して文書を取り扱う機会が増えると、機密情報の漏洩や外部攻撃のリスクが高まります。
これらのセキュリティリスクに備える具体的な対策は以下のとおりです。
- 端末に文書をダウンロードさせないようにする(閲覧権限のみ許可するなど)
- 自宅や外出先などの社外ではプリンタや外部機器を利用させないようにする
- 会社が許可した端末以外からのアクセスを禁止する
また仕事とプライベートの端末を区別できるよう、アクセス制限を行う仕組みを導入することも有効です。
リモートワークでのセキュリティを高めつつ、利便性を下げないよう対策を講じていきましょう。
ペーパーレス化の進め方

ペーパーレス化は、企業の課題に合わせた方法で進める必要があります。ここでは、具体的な進め方について見ていきましょう。
紙を電子化する部分に課題がある場合
紙の電子化に課題がある場合は、「作業を外部に委託する」「AI-OCR(AI技術による光学文字認識)を使って業務を効率化する」などの方法が有効です。
企業内に保管してある大量の書類や紙を電子化するには、多大な時間とコストがかかります。これらの作業を外部に委託したり、AI-OCRを使って業務を効率化したりすることで、紙の電子化を進めつつ、通常業務にも専念できるでしょう。
保管・共有する部分に課題がある場合
保管や共有に課題がある場合は、「文書管理システムを導入する」「法令に対応するために有識者やコンサルタントの力を借りる」などの方法が適しています。
文書管理システムを選ぶ際には、自社システムとの連携性や操作感、自社の業務にマッチしているかなどを考慮する必要があります。
自社の課題を解決するソリューションの活用も考慮する
ペーパーレス化の手段はさまざまであり、現場に合わせたやり方やシステムを活用して進める必要があります。しかし、現場ごとにシステムを選定してしまうと、全体で行う業務に支障が出てしまう恐れがあります。
たとえば、それぞれのシステムで保存したデータが分散することで管理が煩雑化する可能性や、複数の業務データを一括して閲覧する際に逆に効率が悪くなる可能性もあるでしょう。
これらの課題を解決するためには、「データの保管・検索部分をシステムで共通化する」ことが有効です。またデータを検索する部分を共通化しておくと、ユーザーや事業所に応じてアクセス権限を変更できるため、セキュリティの強化やフレキシブルな運用にもつながります。
このように、社内でのペーパーレス化を円滑に進めていくためには、自社の課題を解決するためのソリューションの活用も重要といえます。
まとめ
ペーパーレスの推進によって、業務効率化や環境保全への寄与など、多くの効果が見込めます。ただし、すべての業務のペーパーレス化を一気に進めることは困難であり、業務がうまく回らなくなる恐れもあるため、身近な社内文書から徐々に始める必要があります。
ペーパーレス化の課題は企業によって異なり、適した施策や進め方もさまざまです。自社に適した方法で段階的にペーパーレス化を進め、最終的には社内全体に浸透させていきましょう。
下記のページでは、ペーパーレス化の事例や成功のポイントを詳しく解説しています。ペーパーレス化の導入・定着を進める際の参考にしてください。

活文は「保存管理」「伝達共有」「価値創出」3つの力で企業のペーパーレス化を支援
情報資産であるビジネスデータには、企業の価値が詰まっています。活文は企業のペーパーレス化を整理・管理だけではなく、インサイトの発見につなげ、さらなるビジネスへの成功へと導きます。
関連情報

【専門家監修】日本企業のペーパーレス化の現状とDXへの道
~DXに貢献できる仕組みに変えるには何が必要か?~
2025年6月27日

【専門家監修】ペーパーレスとは?ペーパーレス化を進めるために必要なこと・進め方を解説
2022年8月30日
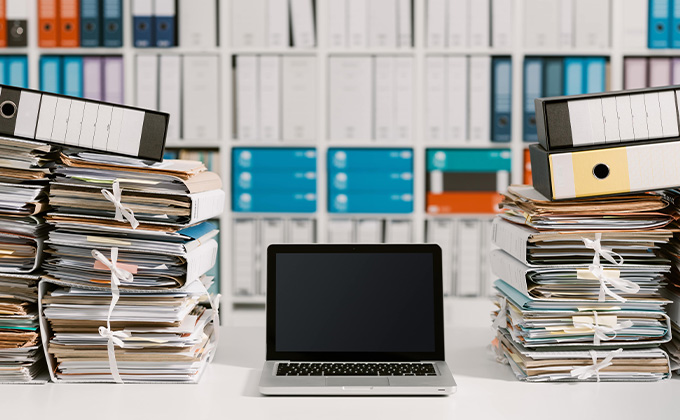
【専門家監修】ペーパーレス化の事例を紹介! 成功企業から分かる3つのポイント
2021年12月1日
ホワイトペーパー

ペーパーレス化の進捗状況に関する意識調査 ~業務効率向上のカギは? スムーズなシステム連携で実現するペーパーレス改革~

経営者層・人事総務担当者に聞いた!ペーパーレス意識調査 ~ペーパーレス導入企業の80%が「ペーパーレスの導入・推進は業務の効率化に役立った」と回答~

企業のペーパーレスによる経費削減調査 ~「1カ月あたり100万円以上コストカットに成功した」企業は50%!~
活文 製品・ソリューション一覧
価値創出
伝達共有
-
コラボレーション
-
大容量高速ファイル転送
-
ファイル保護
-
電子署名・電子契約
-
メールセキュリティ
活文 コンテンツ一覧
※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。